プロの練習を垣間見ると短時間でどんどん仕上がっていく様子が面白くもあり羨ましくもある。
なかなか練習時間が取れない社会人音楽家はそんな「プロ奏者の練習の仕方に秘密が知りたい」「短時間で出来るようになる方法を探したい」と思うことも少なくないでしょう。
今回は短い時間で曲を仕上げてパッと吹けるようになる方法について考えてみましょう。

練習にもスキルが必要
効率を上げて短時間ですぐにパッと出来るようになるためには、まず練習スキルというものが必要です。
つまり
- 短時間で仕上げるための方法をいくつも知っていること
- その時の自分と状況に合った練習法を選ぶ目を持っていること
- 選んだ練習法を実行できること
というものが必要なのです。
これが無い状態で「とにかく短時間で仕上げる!」と考えても、それは実行不可能です。
それではプロ奏者はどうやってその練習スキルを身につけるのでしょうか。
練習上手になるには
プロ奏者はどこからか練習の秘訣を発掘して来るわけではないし、門下秘伝の練習法が存在するということもありません。
ではどうやって練習スキルを上げてきたのでしょうか。
端的に言ってしまうとたくさんの上手く行かない方法を経験するという時間と労力の蓄積をして来たからこそ、場面ごとに効率の良い練習方法を知っているのです。
先生や師匠から教わる方法がたくさんあるにしても、自分に合うかどうかは自分で判断するしかありません。
体力があって時間があるときに無駄な練習もたくさんして、自分に合うものと合わないものを見分ける経験をたくさん積む、というケースがほとんどでしょう。
そういう積み重ねの中で譜読み力や演奏スキルや細部の聴き取り力が上がると選べる練習法が増えていき、実行できる練習法も増えていくもの。
練習が短くすむのは、その前に長く積み重ねてきたたくさんの蓄積があるからこそ。
「パッとできる」のためにはどれだけの時間と労力が必要なのかということですね。

時間をかけるだけじゃダメ
また、ただ単に時間をかければ良いというわけではなく、PDCAを回しながらたくさんの情報から取捨選択して練習方法の選択スキルを洗練させるという作業をしなければ、いつまで経っても「パッとできる人」にはなれません。
だから結局はこれまでに積み重ねてきた知識や経験やスキルがない状態なら、やはりその場その時にたくさんの時間と労力をかけて準備をすることが必要になって来るのです。
これまでの積み重ねがないのに「パッとできる」を気取ってみようとしても、ただの準備不足な演奏になることはわかりきっていますよね。
すぐに出来る人は才能があるように見えるかもしれませんが、あるのは才能ではなく努力と根気と情熱の蓄積です。
必要なステップを飛ばそうとしても先には進めませんから、地道に一歩ずつ進んでいくのが結局は一番の近道なのかもしれませんね。
そんな風に見つけていくものである急いで曲を仕上げるためのアイデアを、この次にいくつかご紹介します。
短時間で仕上げるアイデアあれこれ
ここからは時間がないときに合奏までに譜読みを仕上げる急ぎで練習するためのアイデアをいくつかご紹介します。
ご自身の経験やスキルや体力に合った練習法を選んだり組み合わせたりしてみてくださいね。
ドレミで歌う
急ぎで楽譜の音を並べられるようになりたいときのアイデア一つ目は【ドレミで歌ってみること】です。
よく言われる基本的なことではありますが、何の音を出したいのかを認識するのが第一歩なので、これは楽器で音を出す前に通勤電車の中などで済ませておきましょう。
それから指を動かしつつ同じことをするのも有効ですが、せっかくならこのときには音域ごとに違う吹き心地や抵抗感の違いまでイメージしながらやっていく方が速く練習が進みます。
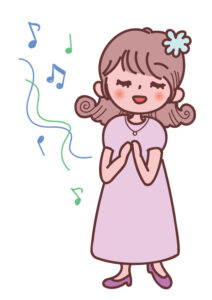
ブレてる音にアクセントをつける
急ぎの時の練習二つ目は【ブレている音にアクセントをつける】というもの。
これはインテンポで吹いてみてほんの少しの転げやモタつきが感じられる音に、テヌートをつけたりアクセントをつけたりして歪みを矯正する方法です。
具体的にフレーズの中のどの音からどの音への接続がどんな理由でうまく行かないかを、吹きながら聴き分ける耳があればこの練習法が使えます。
吹きながらそれが判断できない場合には残念ながら使えません。
その場でもらった楽譜を初見でレコーディングするとき、出来れば一回で録り終えたいものですが、もしもミステイクを出してしまったらせめて2回目では上手くいかせる、そんな場面で必要なスキルですね。
「来月までに練習しておきます」なんて眠たいことを言っていれば次の仕事は来ませんから。
しかし微細なブレを吹きながら聴き取ることが出来ても、もしも息のコントロールが瞬間的に上手くできない状態ではこれまた使えない練習法でもあり、ちょっと難易度は高めかもしれません。
リズム練習をする
アクセントで歪みを矯正する方法が使えない場合、きっと自分では「このあたり一帯がなんか変」というように聴こえているでしょう。
その変だと感じるところ全てでリズム練習を行うことも有効です。
リズム練習とは、楽譜通りではなく付点や三連符にリズムを変えて吹いて、どうにもやり難いと感じるところや何となく引っ掛かりやすいところを見つけていく作業です。
それで引っ掛かりやすい音の接続ポイントが見つかったら、今度はそこだけを取り出して何が上手く行かない原因なのかを調べます。
例えば
・音域が変わるときの息のコントロールが甘いのか
・指の動きが遅いのか
・指と息にばらつきがあるのか
など。
それにもやはり精度の高い耳と分析力が必要ではありますね。
ともあれリズム練習は割と簡単に出来る方法のひとつです。
楽譜をブロックで見る
最後にご紹介する急いで曲を仕上げたい時のアイデアは、【楽譜をブロックで見る】こと。
これは譜読みの手法とも言える、いくつかの音符を大きなまとまりのブロックとして見る方法です。

・上行形なのか下行形なのか
・ジグザグ音形なのか
・繰り返し出てくる形はあるのか
・特定の音が軸になっているかどうか
・どんな旋法が使われているのか
・どんな和音の中での動きなのか
・絶対外してはいけない旋律の核はどの音なのか
ということを俯瞰するのです。
音符を一つずつ順番に追いかけるのに比べたら、音形がどんなパターンで並んでいるかを判断できる方が、音符の認識も全体像の把握も格段に速くなります。
ただしこれは楽譜を見て即座にアナリーゼできるスキルがある場合にだけ使える方法ですね。
アナリーゼに時間のかかる人、アナリーゼ自体が出来ないという人は、やはりドレミを声に出して読んで音の並び方に慣れていくのが一番の近道でしょう。
まとめ
ということでいくつかアイデアをご紹介しましたがこの他にも短時間の練習で仕上げるための手法は無数にあります。
やはりその一つ一つを時間をかけて自分のものにしておくというのが、現場で素早く情報を処理するために大切ですね。
一緒に一歩ずつ地道に行きましょう!



