見落とされがちではありますが、思考や感情、習慣は演奏に大きな影響を及ぼしています。
今回は演奏家のメンタルのコントロールについて、様々な角度から考えてみます。
もくじ

上達を阻む心
下手なままの方が都合がいい
出来ないところはたくさんだけれど、あまり練習はしない。
その場では「練習しなきゃ」とか「次までに見ておきます」とか言いつつ、次の時も全く変わっていない・・困ってしまいますね。
でもそれって実はやる気とか根性とかの問題ではなく、脳の仕組みとしては自然なことかもしれません。
人の脳は変わるということに抵抗を感じるように出来ています。
それは昔々まだ人類が野生状態だった時に、変わらない方が安全だったから。
いつも通りのパターンで行動する方が、敵のテリトリーにうっかり入ってしまうこともなく、いつも通りに食べものが手に入って、新たな冒険やチャレンジをするよりもこれまで通りを維持する方がメリットが多かったのです。

出来ない自分でいても大丈夫という状況を体験したら、わざわざ新しいことが出来るようになる必要は感じにくいもの。
今までと違って出来るようになるために、現在の状況を変えるのは面倒くさいし、ちょっと怖いし。
進歩しなくて良いと思い込むことは、無意識レベルでは安心する材料になります。
今とは違う自分になる必要があると思うためは、今のままだと不都合があったり、「上手になって絶対にやりたいことがある!」などそのままでいることの方がリスクが高い場合です。
音大受験生なんて、まさにそれ。
「専門家として生きていくのに、下手なままでは人生が立ち行かない」と思うから必死で練習するのです。
では趣味でやっている方がこれまで通りではなく、進歩したい欲求を持つのは一体どんな時なのでしょうか。
「一歩進むとこんな風に演奏出来て楽しいよ!」という進歩する快感を、先生や身近な上手な人が提示するというのは目標設定の大きなきっかけになるかもしれません。
楽団に一人でも、「あんな風に演奏したい!」という憧れられる演奏をする人がいたら、周りのモチベーションも大きく影響されそうですね!
「どうせ出来ない」って本当?
「自分の音は良い音じゃない」
「どうせ才能ないから」
「プロになりたいわけじゃないし」
もしかしたらその思考は、
「スター奏者にはなれないもの」
「良い音はこれ、あなたのは違う」
「アマチュアには難しいよね」
そんなどこかで誰かが漏らした何げない言葉を本気にしているだけかもしれません。
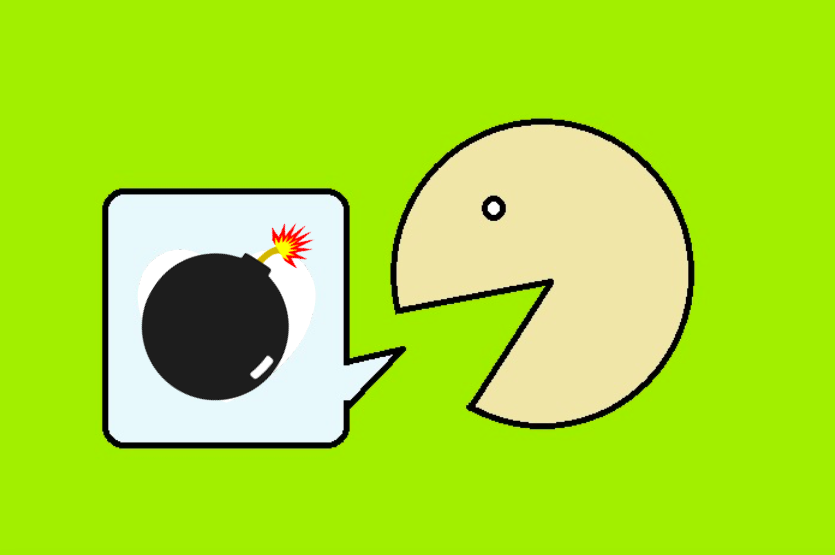
何も比較対象がなくて、誰にも何にも言われたことがなければ、どうでしょうか。
自分の音が良いかどうか、演奏が良いかどうかなんて判断出来ません。
それならば自己否定の思考だって、出てくるわけがないのです。
何にも比較するものがなければ、ただ一音出ただけで楽しくて「自分すごい!」「これ楽しい!」って思いませんか?
きっと楽器に初めて触れた時は誰しもそうだったはず。
ではどうして「自分は大したことない」と思うようになってしまったのでしょうか。
今までの人生を振り返ってみて「あなたには出来るよ!」という言葉と「私たちにはムリだよね」という言葉、一体どちらをよりたくさん耳にして来ましたか?
普段の仕事や楽団仲間との会話ではどちらの言葉が多いですか?
たくさん耳にしている言葉は無意識の思考に刷り込まれていて、まるで自分が最初からそう思ってたような気がしてしまうかもしれません。
でも。
生まれたばかりの赤ちゃんが自分について「どうせ自分はこの程度」なんて思うでしょうか。
そんなバカな話はありませんよね。
いつかどこかで触れてしまったネガティヴな言葉を真に受けて信じているから「どうせ」と思うのです。
果たしてスティーブ・ジョブズは「俺なんかどうせこの程度」と思っていたでしょうか。
逆に自分に対して「出来る」「大丈夫」と常日頃から言い続けてる人は、他人に何と言われようと関係なく「自分は出来るもの」と信じていたりします。
そういう人は出来ないことがあれば何とかして解決策を見つけるし、見つからなければ自分で解決法を作り出してしまいます。
他人の意見を鵜呑みにして萎縮してしまうのと、自分で自分の評価を選ぶのと、一体どちらが人生を快適に、より良く生きられるでしょうか。
ネット上でもリアルでも日常にはネガティヴワードがたくさん溢れてます。
それを真に受けるかどうか、それを自分の評価にするかどうかはあなた次第なのですよ。
当たり前のレベルを引き上げる
「練習してもなかなか上手くならない」
「やれば良くなるとわかってはいるのに着手できない」
そういうことってありがちですよね。
コーチングの理論で「人は自分の心地よいと思う状態から出たがらない」というものがあるそうです。
下手だろうと、コンプレックスに感じていようと、変化することに比べれば現状維持の方が安心、人とはそういうもの。
コーチングでは心地良いと思うレベルを今いる場所より高いところに設定し、【心地よいレベルにいない現状への違和感を解消する】という脳の仕組みを利用してレベルアップするのだそう。
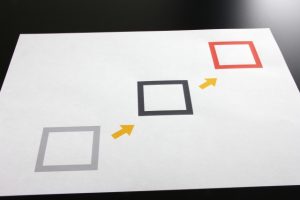
音楽家に置き換えてみると、「上手くなりたければ上手い人と付き合いなさい」「自分が一番下手な状況にいられる人は急激に上手くなっていく」など、よく言われます。
これはある意味で真実です。
当たり前の基準が今の自分よりもステップアップしたところにあれば、自然とそこに違和感なくいられるように頑張りたくなりますもんね。
でもこの理論、メンバーが決まっている楽団ではどう応用したらいいのでしょうか。
普段の楽団の仲間の演奏が一番多く接するものであれば、やはりそれが自分の当たり前になってしまいます。
でもこれは、上達の助けにならない人と付き合わない方が良い、ということではありません。
人間関係は演奏スキルだけでは成り立っていませんから。
今ある状況で、さらにステップアップしたい人に役に立つことの一つは、良い演奏をたくさん聴くこと。
例えば来日演奏家などのコンサートに行くのも良いでしょうし、CDなどで日常的に良いものを耳に馴染ませておくのも良いでしょう。
レッスンを受けているなら、先生にたくさん演奏してもらってたくさん聴くのも大切な要素です。
身近で自分と同じ人種であり、身体構造も暮してる環境の気候なども大して変わらない人に出来ることがこんなにある、と知るのは刺激になりますよね。
上達したければ目指したいものにたくさん触れられるように環境を変えてしまうこと、ぜひ普段出来そうなアイデアにアレンジして応用してみてくださいね!
習慣・思考・気分を味方にする
出来ない・やめられない問題
カフェイン中毒から抜け出す
わたしは紅茶や緑茶など習慣的に飲んでいるカフェイン飲料を辞められないと感じていたことがありました。
カフェインを取りすぎると夜寝つきが悪いし、それによって翌日に疲れが残る。
朝に疲れているから、さらにカフェインに依存する。
そんな抜け出せないループ、経験のある方は少なくないでしょう。
飲んでいる時は無意識なのに、飲まないとなると急にお茶のことばかり考えてソワソワするのですよね。

これは動作だけでは無く、思考の習慣とも言えるでしょう。
辞めたいと思うことは、ただ辞めるわけにはいかないのです。
わたしたちの脳は実行と禁止の区別がつかないので、禁止を意図しても実行のスイッチが入ります。
ということは、何か他のことで置き換えなければなりません。
ピンクの象を思い浮かべないためには、黄色のイルカが必要です。
わたしのカフェイン問題は、
・朝何気なく習慣的に淹れてる緑茶を、ノンカフェインのよもぎ茶にする
・良い香りが欲しい時は手にちょっと良いハンドクリームを塗る
そんな置き換えで何の問題もなく解決しました。
奏法にしろ悪癖にしろ、望ましくない動作習慣をやめたいと思う時には、やめたいことを連想しない別の動作で置き換えていくというのがおすすめですよ。
自分には出来ないという思い込み
「動画の編集なんて難しそうすぎる!一度生まれ変わらなきゃ絶対ムリ!」
そんな風に思っていたのは数年前のわたしです。
とある勉強会で動画を撮って自分のスマホで編集してみる、というワークがありました。
そのときに最初から諦めモードで「絶対ムリ!」と思ってたのです。
でもね。
実際やってみたら10分くらいで出来てしまいましたよ。
実はわたしは大学生の頃、パソコンの電源の入れ方はわからない、ビデオの録画なんて不可能。
というかむしろテレビのスイッチを入れるボタンが何色なのかもわからない。
ちょっとやって難しいと思ったらすぐに諦めてしまうという、やらず嫌いでわかろうとしない、しょうもないタイプだったのです。

みなさんも新しいトレーニングやレッスンに取り組んでみようと思った時に、
「どういう風にやればいいのかわからない」
「これをやってどんな効果があるのかわからない」
「どういう状態が出来てるってことなのかわからない」
そんな風に戸惑いを感じることはあるかもしれませんね。
目指したい状態になるために新しい動作や思考パターンに慣れていくというのは、脳の新しい回路を作っていく作業ですからこの反応は自然なことです。
わたしがまだトレイニーでアレクサンダーテクニークの教師養成コースに通っていた頃、トレイニー仲間からもたくさん「わからないけどわかりたい」という葛藤に悩んでいるという声を耳にしていました。
ダルクローズのリトミックを定期的に学んでいるときにも、一緒に受講してる仲間はほとんどが音大出身の演奏家や指導者でしたが「どの内容も難しくて大変」という声が上がるのは日常茶飯事でした。
でも『出来ないからやめる』という人はいませんでしたね。
そしてやめなかった人はみんなちゃんとそれぞれの学びに習熟して、資格を取ったり仕事で使えるように身につけたりしていきました。
何が言いたいかというと、どんな学びについても言えるのは、今まで全く知らなかったことや新しいことに出会ったときには抵抗感があるものだということ。
その「難しい」「わからない」という抵抗感に負けてやめてしまえばそこまで。
何にも身につかないし、わからないことはそのまま。
全然何も変わらない毎日に戻っていくだけ。
それが嫌で「どうしても変わりたい」「絶対ステップアップしたい」と思うのなら、抵抗感がありながらも続けてみるのも大切です。

わたしが普段やっているソルフェージュのレッスンもそう。
初めてのときにわからなくて出来ないのは当たり前。
だってわからなくて出来ないからこそ、現在問題を抱えているのですから。
そして今までのご自身の概念になかったことなのだから、すぐに理解して身に付けるなんてことは不可能で当然。
最初のわからない苦しいところを抜けるまで、こらえて続けられるかどうかが第一関門になっているのです。
そして続けている生徒さんはみんな
「コンサートで褒められた!」
「リズムが一定のテンポでキープ出来るようになってきた」
「音痴な気がしていたハーモニーがきれいにハマるようになった」
などの成果を少しずつでも確実に手にして行っています。
新しいことがわからなくて出来ないのは当たり前。
その段階で諦めてしまわずに根気よく向き合うこと。
知らなかった分野に挑戦するときや専門外のことを学ぼうと思った時に、心がけていたいことの一つですね!
気分・性格を変える
性格は変えられる
「本番前にくよくよしてしまうのは仕方ない」
「ミスをしたらナーバスになるのは性格だし」
でもちょっと待って。
それって本当でしょうか?
先日心理学系の勉強会に参加したときに、そこで講師をされてた方がはっきり断言していたこんな言葉が印象的でした。
「性格は思考の習慣だから変えられます。」
なるほど、確かにそうですよね。
くよくよしがちな性格は『解決しない悩み方を繰り返す』という自分の思考選択の習慣。
ケンカ早い性格は攻撃的な思考選択の結果。
ポジティブな性格は物事の良い面を見る思考習慣。
思考は偶然勝手に自動的に出てくるものではなく、自分で選んでいます。

お腹が空いたときに道端に落ちてるものを食べないとか、他人が注文したものを横取りしない。
そんなことは当たり前ですよね。
「偶然隣の人のご飯を食べちゃった」なんてことはあり得ません。
ちゃんと食べるものは選びます。
それと同じで何か反応したくなったときに、どんな反応をするかは自分の選択次第です。
勝手に感情や反応が出てくると感じるのなら、コントロールしないで垂れ流しにする習慣だということ。
それでは感情が不安定になってしまい、人間関係を上手く行かせるのも難しいのではないでしょうか。
ある出来事に対して怒るのも、嘆くのも、喜ぶのも、楽しむのも、あなたの選択次第。
マザーテレサの言葉をこの頃はSNSなんかでもよく見かけますよね。
思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。
言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。
行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。
習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。
性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。
性格だからと諦める必要なんてありませんね。
他人の性格を変えたい!
「あの人もっと真剣に練習してくれたらいいのに」
「もっと情熱を持って演奏できないのかな?」
合奏に参加していたら、きっとそんな風に感じる機会はたくさんあるでしょう。
それでは他人の性格を変えることは果たして出来るのでしょうか。
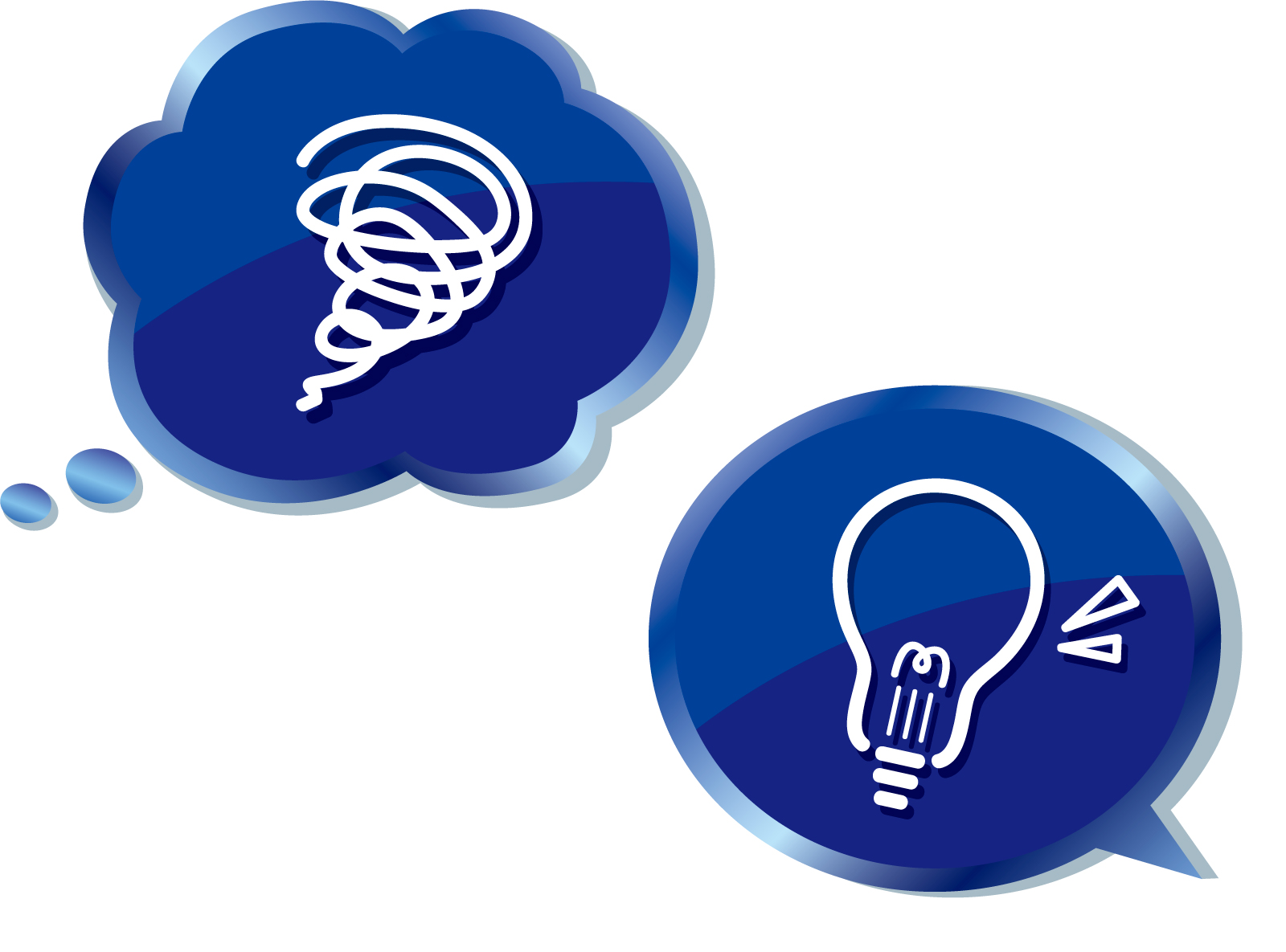
これは結論から言ってしまうと、ムリです。
自分の思考は自分で選べますが、他人の思考はあなたが選ぶことはできません。
お友達の代わりに考えてあげる?
そんなこと出来るわけがありませんよね。
出来るのはあなたの考えを提案することだけです。
受け入れるかどうかは相手次第。
成年後見人をつけるような認知症の人だって、代理人は代わりに考えてあげているのではありません。
代理人としては認知症の方にとって最適であろうことを、自分で考えて選択しているだけ。
誰かの性格や思考をコントロール出来るのなら、世の中に失恋する人はいないはずですよね。
他人の性格や思考をコントロールしようとするのは時間と労力のムダであり、それが出来ないことを嘆くなんてバカバカしいの極み。
木になってるリンゴが落ちるように一生懸命念じてるのに、全然落ちる気配がないと嘆くようなものです。
他人の言動という刺激に対してあなたが出来るのは、自分自身の思考と反応をコントロールすることだけ。
それがアドラー心理学の「課題の分離」です。
自分のコントロール範囲と相手のコントロール範囲をごちゃ混ぜにせず、きちんと分離して考えましょうということ。
例えば不愉快な出来事に出会ったら、相手を変えようとするのではなく自分の受け取り方を変える。
労力をかけたいのはそういう部分ですね。
他人の言動が気になってしまう方は、ぜひ心に留めておきましょう。
気分は身体で変えられる
同じように不愉快なことが起きた時、
・感情的にイライラする
・冷静に出来事として受け取る
など、わたしたちは自分でどんなを反応するのか選択しています。
イライラするのはイライラさせる相手の問題ではありません。
ただの事実としての出来事から、イライラするという選択をした自分の問題です。

そして、自分できちんと感情の選択が出来るかどうかは、身体の使い方が影響しています。
ためしに頭と首と背骨を動かさずに10歩くらい辺りをぐるっと歩いて戻ってきてみましょう。
どんな気分ですか?
ずっとその動き方をしていたら一日の終りにはどんな気分になっていると思いますか?
ではもう一つ。
頭も首も背骨も腕も足も胸も全部が自由に動いて良い、と思って10歩くらい辺りをぐるっと歩いて戻ってきてみましょう。
さっきとどう違うでしょうか。
2回目の方がずっと快適で気分も良かったはず。
ほんの些細な違いかもしれませんが、その些細な違いに着目できるか見逃すかというアンテナ感度も反応を選択する上で大切です。
こういう身体の使い方のメンタルへの影響って意外に大きいもの。
・イライラした時
・不安になっている時
・悲しい気持ちが出てきた時
身体の使い方を改善してみるとどんな変化があるのか、試してみると意外な発見があるかもしれませんよ!
自分と他人を尊重する
他人との関わり
望まない人は助けられない
変な吹き方をしていたり、おかしな音を出している人を見かけてしまってすごく気になることってありませんか?
気になってしまったときには何か手助けをしたくなるかもしれませんが、本人が「手伝ってほしい」「助けてほしい」と思っていない限り、周囲の人間に出来ることは何もありません。
本人が望むことなら他人が手助けできますが、変化を望まない人を変えることは誰にもできないのです。
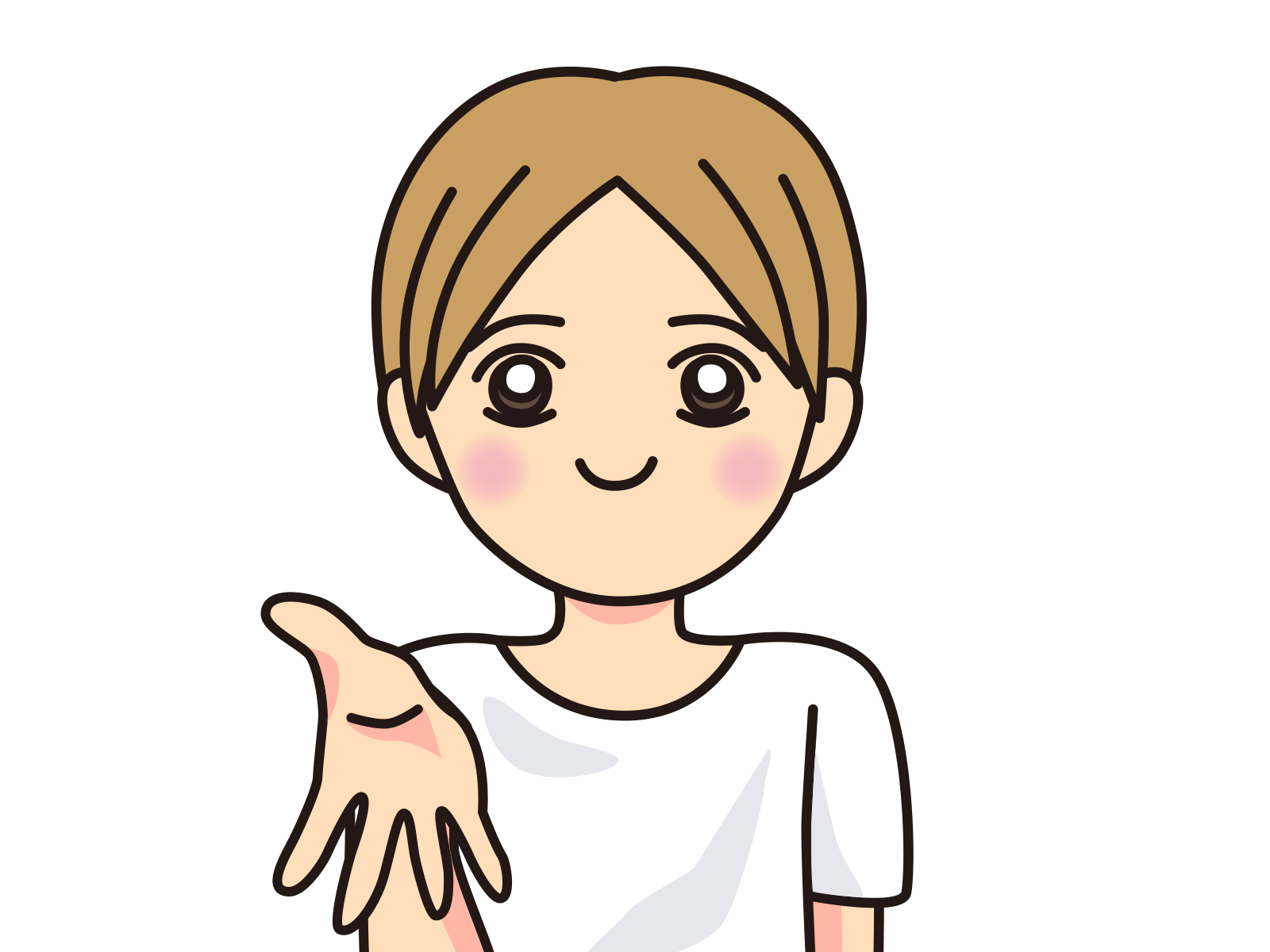
どんなにぐちゃぐちゃな姿勢だろうと、変な音になっていようと、どこかを痛めていようと、本人が「それをやめたい・良くなりたい」と思うことが改善のための第一歩。
本人が望まないことを、わたしたちが正しいと思うからって押し付けても、それは自分の自己主張です。
その場ではお礼を言われたとしても「あなたの自己主張したい気持ちはわかりました」というだけの意味かもしれません。
実はわたしは発達障害コミュニケーション指導者という資格を持っているのですが、参加した研修会で印象に残っているのはこんなこと。
・発達障害は本人や周りが困っている場合にのみ問題になる
・特性によって困りごとが発生していないのであれば、それは問題ではない
発達障害の場合はここに周りの環境をどう整えるかということが関係してきますが、上記2つのことについては楽器演奏に関しても同じように考えられるでしょう。
きれいでなくても楽器で音が出せれば満足かもしれないし、もしかしたら楽器をコレクションするのが趣味であって音が出るかどうかすら興味がないかもしれません。
そういうタイプの人に「アナリーゼをしましょう」と言っても、余計なお世話以外の何ものでもないでしょう。
本人が改善を望んでいない場合は、改善の必要はないのです。
その代わり、「今の状況を変えたいから手助けしてほしい」と言われたら出来ることはしてあげたいもの。

自分の基準で変に思えることでも、必ずしも相手が同じように感じているとは限りません。
何か伝えた方が良いいのかどうか迷ったら、相手がどんな意図でそれを行なっているのかをまずは尋ねてみるのも良いかもしれませんね。
相談する相手を選ぶ
「何だかうまくいかない」「奏法や仕掛けを変えようか迷っている」そんなとき、楽団の仲間や身近なお友達などに相談してみることってあるのではないでしょうか。
もちろんそれがいけないということはありません。
ですが共感して欲しいだけならともかく、本当に有効なアドバイスを得たい場合には相手を選ぶ必要があります。
相談するのが自分と同じような感覚を持っている人や、自分と考え方が近い人では話が堂々巡りになってしまい、実際の解決に繋げるのは難しいもの。

ビジネスシーンでも、コンサルティングを受けるなら自分の目標とすることを達成したことのある人に方法や問題点を尋ねるでしょう。
自分と同じく行き詰まってる同士で悩み相談をし合っても埒が明きません。
困ったときには自分と違う考えや、自分以上の能力を持った相手に相談するからこそ、自分だけでは見つからなかった発想とか視点を得ることが出来るのです。
音楽においてはやはり先生やトレーナーなど、信頼出来る耳を持っていて的確な意見をくれる相手に話を持ちかけてみるのが良いでしょう。
「これ、どうかなあ」
「どうだろう?わからないねえ」
と言い合いたいだけなら、一緒に悩んでくれる自分と近い感覚の仲良しな仲間と楽しくワイワイするので充分。
でも本当に何か解決したかったり的確な意見が欲しい場合は、誰に相談するかが大切になる場面もあるかもしれませんね。
全ての人は特性を持っている
以前、発達障害コミュニケーション指導者の資格取得に際して学んで印象に残っている言葉、それは「全ての人には何かしらの特性がある」ということ。
本来誰しも何かしらの個性や特質を持っているものであり、そこに正常も異常もない。
何かしらの特性によって困っていることがある場合、そこにサポートの必要が生まれるということ。
明確な境界というのは存在しないのです。
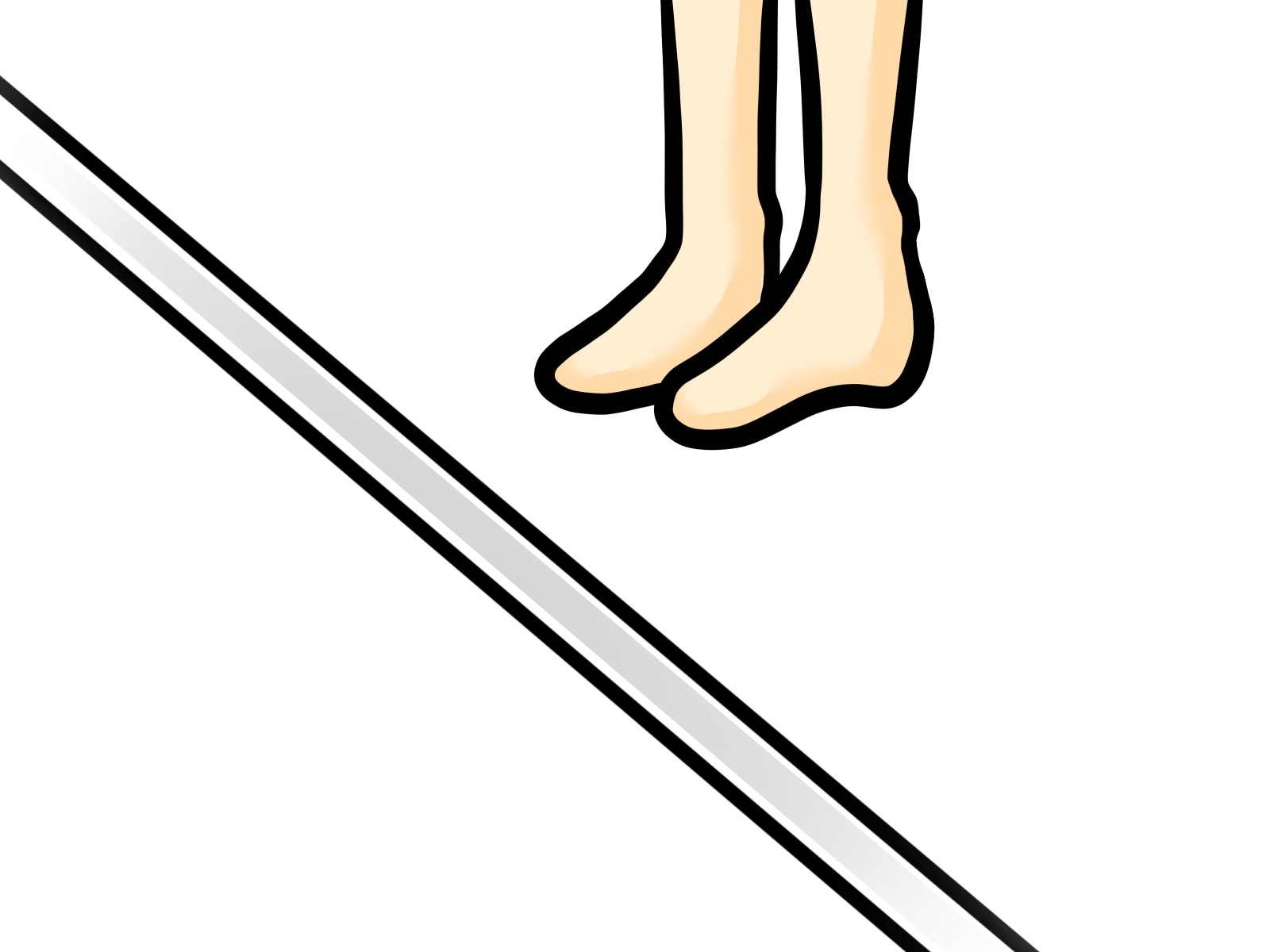
繊細すぎてすぐに心が傷ついたり、練習に没頭しすぎて周りが見えなくなったり、気になる細部にこだわりすぎてしまったり、そういう特性は音楽家として生きるためには強みになります。
でもそれが弱点になってしまう環境だってあるでしょう。
周りの環境が自分の特性に合わなければ不幸になってしまうかもしれません。
でも自分の特性を活かせる環境に身を置くことができれば、持っている特性はチート能力です。
あなたの周りにちょっと変わっているなと感じる人はいませんか?
その人は「関わらない方が良い変な人」ではなく、別の場面ですごい力を発揮する可能性のある人です。
プロ奏者の中にはアマチュア奏者を見下すような人間もいますが、音楽についてアマチュアでいることを選んだ人は別の分野でのエキスパートでしょう。
それは仕事かもしれないし、子育てなどのスキルかもしれないし、別の趣味に関してかもしれません。
また、演奏する人に限って考えてみても様々な特徴を持った人がいますよね。

音色は極上に美しいけど、アンサンブルは苦手な人。
周りとのコミュニケーションは上手で人気者だけれど、演奏技術が飛び抜けているわけではない人。
個人練習の中で探求を深めていくことは得意だけれど、人前で演奏を披露することは得意ではない人。
逆に人前でパフォーマンスすることは大好きだけど、専門的に探求を深めるような作業が苦手な人。
どれもただの特徴であり、個性です。
どこにも優劣はありません。
自分の特性を把握できたら人生が楽になるかもしれませんね。
でもそれより大切なのは、みんな違って当たり前だと知っていること。
誰かの特性が自分の特性と噛み合わないからとストレスを感じるのは不毛です。
違うのが当然であり、共感できないことがあるのも当たり前。
そういう前提で生きている人が増えたら、世界中にある争いごとはずいぶん減るのではないでしょうか。
音楽の話からは外れてしまいましたが、完全にオリジナルの楽曲を無伴奏で演奏するのでない限り、音楽をする上で人間関係が発生しないことはあり得ません。
何かの時に思い出して役立てていただけたら嬉しいです。
自分を大切にする
失敗したことを何度も思い出す
「本番でリードミスが出てしまった!」
「大事な場面で間違えちゃった」
「もっと準備しておけば・・」
そんな本番後に悔いが残ることって演奏していると多々ありますよね。
ついついやってしまったことや、どうしても出来なかったことを何度も思い出して、自分を罰するような気持ちになってしまうことも少なくないでしょう。
そんな時って心に痛みを感じるのが普通であり自然な反応です。
そして次の機会にはその教訓を活かして準備したりと役立てていくのですよね。
それが反省するということ。
では。
落ち込んだり胸に痛みを感じないと次に何かを活かすことは出来ないのでしょうか。

冷静に考えてみるとそんなことは決してないとわかるでしょう。
でも何となく心にダメージを負わないと許されないような気がしてはいませんか?
申し訳なさそうにしないと周囲の反感を買ったりするかもしれませんし、社会生活をする上で「落ち込んでるフリ」が必要なこともあるでしょう。
とはいえ。
「何が余計で何が足りなかったのか」
「じゃあ次のときにはどうするのか」
そういう次回への改善プランを含んでいない痛みの反芻は、建設的な反省ではなく役に立たないただの後悔。
後悔はただ自分の感情を味わう行為でしかなく、そんなことはしたってしなくたって本当はどちらでも良いのです。
悔しい思いは胸を痛めるためでなく、次への建設的なプランにつなげて行くためのもの。
自分を罰して胸を痛めることは全然建設的なプランではないので、ある程度痛みを味わって気が済んだら忘れてしまいましょう!
そしてきちんと次に繋がる「反省」をして、今回起きたことからの情報を役立てていきたいものですね。
反省と後悔は違うということ、頭の片隅においておきましょう。
一瞬だけの我慢のつもりが
「今だけ乗り切れれば良い!」
「ちょっとだけのことだから我慢しよう」
そんな風に不本意だったり、違和感がありながらも通り過ぎてしまうことは、忙しい日常の中では少なく無いでしょう。
ですが、ちょっとの違和感や些細な引っかかり、日々そういうものに目を向けない習慣でいると、それが続けたときにトラブルに繋がる、心や身体じぇの負担であることのサインを見逃すことになってしまいます。
音楽に限った話なら最悪演奏が出来なくなる程度で済みますが(人によってそれは大問題ですが)、心身に怪我を負ってしまったら音楽どころではなく人生そのものに影響してしまうこともあるでしょう。

極端な例を挙げるなら、
・挨拶するのをサボるのがクセになり、話しかけてくれる人が減って孤立してしまう
・無茶を押し付けてくる人を我慢して耐え続けたあげく心の病気になってしまう
・身体の痛みによって日常動作で出来ないことが出て生活が不自由になってしまう
そんなことは大事故や大事件からだけでなく、小さなトラブルに目をつむり続ける習慣から生まれてくることも多いものです。
「一瞬我慢すればそれでいい」
そんな考えで小さな問題を放置するのは、実はかえって問題を大きくすることにもなりかねません。
自分にとっての小さな違和感にNOを言うことは我儘ではなく、将来の自分自身を大切にすることに繋がります。
・本当は疲れてるのにお酒を飲む
・大事な趣味の時間を後回しにする
そんな一見どうということのない心身への負荷は、今は大したことのないように見えたとしても後で取り返せない大きな後悔になるかもしれませんよ。
音楽だけでなく、あなたは毎瞬本当に選びたいものを選んでいますか?
おわりに
自分の思考・感情・習慣と丁寧に向き合うことは、演奏技術を磨くことと同じくらい大切です。
「メンタルの問題は気合いと根性で解決する」というような雑な力技ではなく、きちんと仕組みを知って適切にコントロールすることを考えていけると演奏も人生もより良くなっていきます。
心の問題は楽器や身体の操作に比べて見落とされがちだからこそ、意識的に取り組むことで大きな差が生まれます。
ぜひこの記事をきっかけに、心のコントロールについても考えていってくださいね。



