不用意なダメ出しを受けて心にダメージを受けてしまったり、その後の演奏動作が不自由になってしまうケースは少なくありません。
とはいえ改善が必要な場面で何も伝えないと言うわけにもいかない現実もあるでしょう。
今回は問題になりがちなダメ出しと、演奏のためのより良いコミュニケーションについて考えていきます。

中学生にも出来るダメ出し指導
学校吹奏楽現場で先輩から後輩にされる指導、よくあるのが音程やリズムがずれているという指摘です。
これ、お互い学生同士であれば素直に聞いていることがほとんどだと思います。
ですが大抵の場合、管の抜き差しでその場しのぎの対処をして終わり。
今後どうしたらいいかまでは、わからないことがほとんどではないでしょうか。
はっきり言って音程やリズムはわかりやすい要素ですから、「ズレている」と指摘するだけなら簡単で誰でもできます。
自分だって指導の専門家ではない学生さんの後輩指導がついついそうなってしまうのは仕方ありません。

でも大人で、音楽や演奏の指導を仕事にしている人がそれでは困ります。
・なぜズレが起きているのか
・改善するために出来ることは何か
・今後どういった点に着目すると再発を防げるのか
そういうことを含めて提案するのがアドバイスです。
起きていることには必ず原因と結果があるので、「今は偶然上手く行かなかっただけからもう一回」なんていうのはプロの指導ではあり得ません。
そんな生ぬるい思考で練習を行い、本番でやはり偶然上手くいかなかったらどうするのでしょうか。
「気持ちをひとつにしてもう一度」なんていうのも、実際の動きとして何をどう変えたらいいかがさっぱりわからないのでダメ。
優秀な指導者はなぜズレたのかを理解していて、それに対する的確なアイデアを提案できるものです。
そのためにトレーニングを受けたり現場でたくさんの経験を積んだりしてきているのですから。
ただのダメ出しなら誰でも出来る。
楽器を手にして2年目でしかない中学生だってやっています。
だたのダメ出しではなく、その先に進む手段を提示するのが先生やトレーナーに求められている役割のはず。
趣味で演奏していてたまに中高生に教える機会があるという方も、単なる学生の延長にならないために頭の片隅に置いておきたいことですね。
ダメ出しの効果
ダメ出しでは上手くならない
「その奏法は間違っているよ」
「音程が合っていないね」
そんな風に合奏指導でダメ出しを行うと、どのような効果があるのでしょうか。
「自分はダメなんだ」
「上手くないからなー」
「どうせ趣味だし」
そんな風にネガティブな気持ちにさせてしまうことが多いのではないでしょうか。

・上手くなってほしい
・もっと楽しめるようにしてあげたい
そんな願いがあってするダメ出しだとしても、萎縮させたり自己否定させたりしてしまうなら逆効果。
本当に上手くなるための声がけはダメ出しではないのです。
上達したい人が本当に知りたいのは、
❌どこがダメなのか
ではなく
⭕️今やっていることが行きたい方向に近づいているのどうか
ということでしょう。
正しい方向に進んでいるのであればそのまま頑張れば良いし、そうでないなら違う方向に向かう手立てを探さなければなりません。
ただのダメ出しではそのどちらも選択できないのです。
ダメ出しをするのは簡単だし教えてる感があるのでついついやってしまいがち。
ですが、人になにか伝えることを「ついついやっちゃう」などのぼんやりした思考で行うのは失礼であり傲慢です。
合奏やパート練習をするならどんな声がけをすると良いのか、なども考えて選択したいものですね。
逆効果になるダメ出し
仲間の演奏者や生徒さんに対して「これを指摘しなくちゃ!」と思うことはあるでしょうか。
もしも合奏中にお隣でとんでもない音程で吹かれたら、気になってしまうものですよね。
そんなときに単純に「ここの音程をどうこうして」とアドバイスしようとしてもなかなか受け入れてもらえないし、相手を萎縮させてしまって逆にミスが増える、そんなことにも繋がりがちです。

そういうときはやたらと口出しする前に一度立ち止まって考えてみましょう。
例えば、隣の席の人が変な音程で吹いているなら、それはなぜなのでしょうか。
周りのハーモニーが聴き取れていないのかもしれないし、聴き取った上でそれが正しいと思って出しているかもしれません。
または周りがずれていてどこに音程を寄せるべきか迷っているのかもしれません。
他にも楽器の具合が悪いのかもしれないし、運指を間違えて覚えてしまってるという可能性も。
色々な理由が考えられますが、やっていることには必ず何かしらの事情があるはずです。
それが何なのかをこちらで勝手に判断する必要はありませんが、本人が正しいと思ってやっていることを頭から否定してしまえば、コミュニケーションが成り立つわけがありません。
「今のは自分にはこう聴こえるけど、それはどういう意図でやっているのですか?」
なんて単純に疑問として尋ねてみるだけでも、相手にとっては考えたり自分を振り返るきっかけになることは多いもの。
流行りはこういう歌い回しだとか、普通はこうやるものだとか、作品によっては色々なイメージを持ってるケースもあるでしょうが、「この人はダメだから自分にとっての正解を伝えなくちゃ」なんていうのはおかしな話。
手当たり次第にアドバイスをしまくって「自分は間違ったことをしていた」と思わせてしまっても、萎縮させるだけで誰の得にもなりません。
自分が思ってることと相手の意図、ぜひとも両方とも尊重したコミュニケーションの取り方を考えていきたいものですね!
良い状態で演奏するために
「思ったような演奏をするために、本番を良い状態で迎えたい」
楽器プレーヤーなら誰でも考えることでしょう。
本番に向けてたくさん練習をして、体調も整えて前日にはお酒も控え、そんな風にコンディションを作っていく方は少なくないはず。
ここではそれにプラスして、コンディションを整えるために心がけたいことを考えてみましょう。
本番直前のメンバー間のコミュニケーションについてです。
快適に演奏するためのダメの伝え方
メンバーの中に名前も知らないような人がいるよりは、仲良し状態の方がアンサンブルはもちろん吹き心地も良くなるもの。
また、本番直前に「アレが変だ、これが下手だ」などダメ出しテロに遭ったら不快・不安な気持ちで本番に臨むことになってしまいます。
快適な人間関係があるかどうかは、結構演奏の質に影響するのですよね。
とはいえ、音響やバランスなど調整したいことがあるのに気を使って言わない、というのもおかしな話。
だからこそ、発言が必要とされている場面では、伝え方を考えましょう。
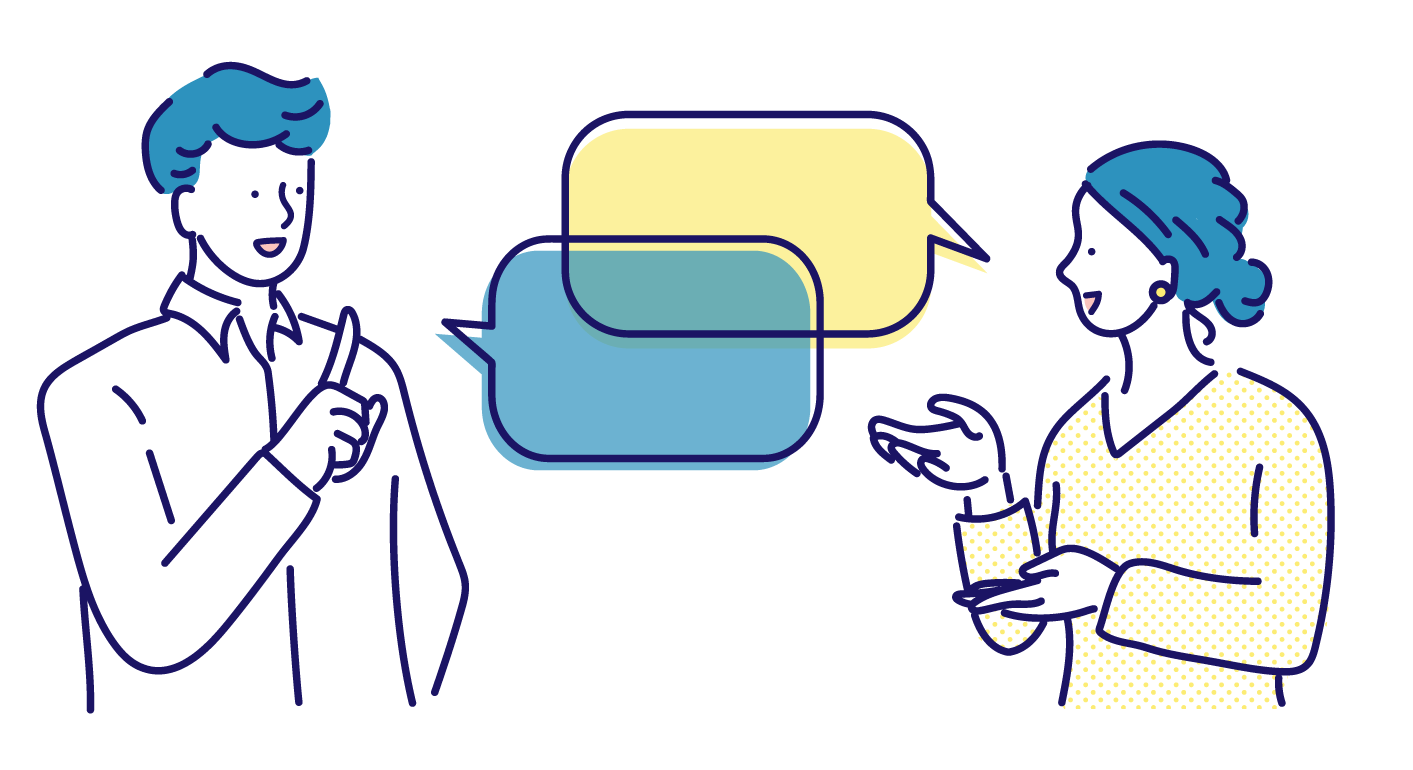
(1)「そこはそれじゃダメだよ!」
(2)「あの・・もしも無理だったら別にいいんだけど・・できればもうちょっとこう・・」
(3)「ここはこんな風にやったらもっと良くなると思うんだけど、どう思う?」
この中ならどれが一番お互い快適に本番を迎えられる提案になると思いますか?
人それぞれ場合それぞれですから、どれが正解ということはありません。
それでも、怒られるとかオドオドされるのが快適だと思う人は少ないでしょう。
相手に何か伝える方法は何通りもあります。
「自分の言いたいことを言えさえすれば、どんな伝わり方をしようと、その後相手にどんな影響があろうと、お構いなし!」
というのはコミュニケーションとして幼稚すぎます。
本番前にダメ出しテロを行うのは、どちらかというと自己満足に近くて相手の演奏を良くするどころか逆効果になる行為のことも少なくありません。
なぜ今それを言うのかだけでなく、なぜその伝え方を選んだのかにも、意識的になりたいものですね。
普段もそうですが本番前は特に、自分も相手もお互いを尊重しながらリクエストをオープンに伝えるよう心がけていきましょう。
ミスを引き出す声がけ
絶対にミスを『しない』演奏と、ミスしてもいいからチャレンジを『する』演奏、あなたはどちらを目指したいですか?
何かを「しない」と思うより、別の何かを「する」と考えた方が、身体は快適に動けます。

新たなことを身に付けるときやパフォーマンスを行う時など、危機感に煽られながら行う場合と安全が確保された環境で行う場合、どちらかというと安全な場所でやる場合の方が質が高くなるというのはすでにずいぶん知られて来ています。
これって自分が演奏するときや練習する時はもちろんですが、本番前に仲間や生徒さんに言葉をかける場面でも同じことが言えるかもしれません。
「絶対うまくやろう!」
「失敗は許されないよね!」
そんなことを言い合うグループと
「ミスは起こるものだから、それも含めて思いっきりやろう!」
と言い合うグループでは、どちらがチャレンジのある表現やイキイキとした演奏を出来るかは容易に想像できるでしょう。
失敗が許されない思考では、何かをやるというよりもやらないことに注意が行きます。
反対に、現実的に起こりうる可能性のあるミスから目をそらさずに認識した上で行いたいことを意図するのは、逃げでも甘さでもなくより良いパフォーマンスをする為の建設的な姿勢です。
「ちょっとでもミスしそうなチャレンジなんて許さない」
そんな役に立たない決め事にお互いに縛られていたら、たくさんの繊細な動きが必要な演奏動作はやりにくくなってしまい、結果的にミスは増えます。
『どんなことが起きてもお互いにフォローし合える』という信頼感は、思い切ったチャレンジをするためにとても支えになります。
あなたは普段本番前に仲間や生徒さんにどんな言葉をかけていますか?
無意味なダメ出しをされたとき
「下手って言われたのがショック」
「何だか馬鹿にされてる気がする」
そんな風に思ってしまうこと、ありませんか?
たしかに誰かの口から自分を否定する言葉を聞いたらイヤな気持ちになりますよね。

もしかしたら確かに改善できることはあるのかもしれません。
それでも傷付いたり苛立ったりする気持ちが出てくるのは自然なこと。
ここで自分の心を守るために頭に入れておきたいことがひとつあります。
それは誰かの口から出るあなたの評価は、所詮その誰かさんの個人的な考えでしかないということ。
そしてその誰かさんの評価を受け入れるかどうかを決めるのは自分です。
誰かさんの評価を自分にレッテルとして貼るかどうかは、あなたが選べるのです。
誰かさんがあなたを否定しても、あなたが同じように自分を否定することを選ぶかどうかはあなた次第。
もちろん信頼している先生やいつも建設的な意見をくれる耳が肥えたお客さんなど、「この人意見は取り入れたい」ということもあるでしょう。
そういう人のコメントは大いに参考にすれば良いのです。
でもネット上の顔も見えないし自分の名前も名乗らないような無礼な相手からのコメントや、無記名アンケートの悪口や、トイレで聞こえる陰口などは、相手にしないという選択肢もあります。
あなたを成長させてくれる前向きな気持ちにさせてくれる建設的なコメントでなければ「名乗って意見を伝えるほどの確信も自信もない人の戯言か」と聞き流す。
そういう姿勢は、あなたの心が疲れて音楽を嫌いになってしまうのに比べたら、ずっと良い方法かもしれませんよ!



