上達が足踏みしてしまう場合、多く見られる傾向というものが存在します。
今回は過去に筆者が陥っていた上達しない練習や思考をいくつかピックアップしてみました。
これを読んだ方はぜひ反面教師にして上達するループに入っていってください。
もくじ

音出しのタイプによる上達度の違い
朝イチで音出しをするときに、上手くなる人とそうでない人は違ったやり方をしています。
・マウスピースや頭部管だけでとりあえず音を出す
・楽器付きで何となくパラパラと吹いてみる
・部屋の広さや気温湿度を考えてどんな音でどんな残響になるか注意して聴きながら吹く
あなたはどのタイプでしょうか。

3つ並んでいるとどれが良さそうか想像がつくかもしれませんね(笑)
どれもちゃんと意図があれば間違いということはありません。
そんな中でも、ちょっと音出しを聴いただけで「あんまり上手ではなさそう」という感じがしてしまうのが、とにかくパラパラ吹いてみる場合。
吹いている本人が出ている音をよく聴いていないために、鳴らない音があったり、指が転げていて音の長さが全部違っていたり、音量にばらつきがあったり、そんなデコボコな不具合をそのまま疑問もなくスルーして別の音形を吹き始めるパターン。
はたから聴いていると「どうしてこの状態で平気で違う音形に移る気になるんだろう?」という音出しをしていることって往々にしてあるものです。
鳴らない音があれば仕掛けや楽器の不具合を疑う必要があるし、
音の長さが均一にならなければ指やキーやタンポの具合が何か変なのかもしれないし、
音量にばらつきがあるなら何かしらブレスコントロールが上手く行かない理由があって改善する必要があるはずだし。
そういういつもと違うことや演奏に差し障りそうなことを早期発見して対処するのは音出しの目的の一つです。
注意深く聴かずにむやみやたらに音を出すのは、暴走族が交差点で意味もなくバイクをふかすのと同じ。
音出しというのはその日の自分や楽器のコンディションを調べたり、動きに慣れて響きを増やしたり、会場の音響に慣れたり、という意味があってするもの。
何にも考えてないなら何の効果も情報も得られるはずはないし、何も聴いていないなら音響なんてわかりようがありません。
意味のないことをして時間を無駄にするだけでなく、ロクに音を聴かない習慣を作るということになってしまうのです。
おまけに無駄にうるさい音出しをして近くで練習してる仲間に迷惑をかけていたりしたら最悪ですよね。
まずは何が知りたくて何のためにその動きをするのかを明確にする、大切にしていきましょう。
あなたは普段、どんな音出しをしていますか?
当たり前の原理原則
雨が降っていたら傘をさせば濡れないですむけど傘をささずいくら気合いを入れたって濡れる。
取り入れるカロリーより消費するカロリーの方が少なければ太る。
収入がなくて支出ばかりならお金は減っていく。
譜面台の上に楽譜を置いたら見える高さに楽譜がいるけれど、何もない空中に楽譜を置こうとしたら床に落ちる。
身体の関節のないところを曲げようとしたら怪我をする。

そんな当たり前のことはみんな、ちゃんと世の中の原理原則に沿って起きています。
同じことで、練習して自分で思ったように演奏できるようになるには、正しい手順とある程度の時間が必要です。
もしもたくさん練習してるつもりなのに全然うまくならないなら、何かしら原則違反がある証拠。
例えば
・時間が足りていない
・手順が間違っている
・必要な情報が不足している
など。
うまくいかない方法でいつまでも練習し続けるのは、体重計の上で1gでも軽くなろうと精一杯力むようなトンチンカンなことかもしれません。
何事もうまくいくための原理原則を知っているかどうかは重要です。
楽譜はただ眺めていれば情報が入ってくるわけではなく、きちんと読み方を知っているからこそ行間の意味がわかります。
アンサンブルだって何となく一緒に音を出せば合うわけではなく、誰のどの音にどうやって寄せたら良いかわかっているからこそ合わせられるのです。
練習の手順だって、心と身体の仕組みを知らないまま、やみくもに100回繰り返すなんてうまくいくほうが奇跡です。
そういう音楽における原理原則に違反してしまうと、どんなに努力を重ねても上達するのは難しいもの。
継続的な努力をきちんと結果につなげたいのであれば、当たり前の原理原則について知っておくことも必要ですね。
以下、原理原則に違反して上達できない例をいくつか挙げていきましょう。
上達出来ない例あれこれ
やたらと難しい曲を吹きたがる
わたしがクラリネットのレッスンを初めて受けた頃、当時師事していた先生から「指示したもの以外に難しいのを練習したとしてもムダですよ」釘を刺されたことがあります。
当時わたしは実際以上に自分が上手にクラリネットを吹けるような気になっていて、先生が指示してくださる課題が「簡単すぎるのでは?」なんて思っていましたが、先生にはお見通しだったのです。
恥ずかしい。。
先生がレッスンの課題として提案する教材は、生徒が抱えてる問題を確実にクリアするためだったり、新しい刺激に触れるためだったり、その時々で明確な狙いがあります。
それはどういう手順を取ると上手くなっていくかを知っている専門家だからこそできる提案です。

自分にどういうトレーニングや手順が必要なのかわかっていない素人が適当に選んだ教材が、専門家の提案よりも上達の助けになることなんてあるわけがないのです。
むしろ順序立てて上達の階段を登れるように考えている計画をめちゃくちゃにしてしまうので、逆効果になることだってある。
そういうことをわかっていなかったのです。
先生はレッスンでたった一音聴いたら、もうそれだけで生徒がどういう練習をしてきたか、またはしていないかが丸わかり。
「余計なことをして変なクセをつけてきたな」と思われていたのでしょう。
わたしも教えるようになってそれがすごくよくわかります。
一見遠回りに感じるような、根気の必要な練習をまじめにコツコツとやる人は、ものすごく早く上手くなっていきます。
反対に一見近道に感じられる、自分のレベル以上の課題ばかりやろうとする人は、なかなか上手くはなりません。
そしてやはり最初の一音を聴けば、どんな練習をしてきたのかはわかってしまうのですね。
「こんな練習をしてきましたね」とわざわざ言われなくても、気付かれているのですよ。
あなたはレッスン前の練習にどのように取り組んでいますか?
「出来た」は本当に出来ている?
ゆっくりのテンポから始めて出来たら少しずつテンポを上げていくような練習、進めて行くとだんだん出来ていたはずのことが上手く行かなくなったりしませんか?

それは練習の段取りに問題があるわけではなく、「出来た」として次に進む基準が甘いことが原因のことが多いのです。
どういうことかというと、テンポ40ではストレス無く出来たパッセージでも、だんだんテンポを速くするうちにちょっとだけ鳴りにくい音が出てきたりします。

ほんの少し音量にでこぼこはあるけれど一応聴こえてはいるし、「まあいいか」と放置してそのまま次のテンポに進みます。
さらに速いテンポではその鳴りにくい音はもう少しだけ音量が下って聴こえます。
「でもまあ無音になってるってわけじゃないし、できたできた」
そんな調子で練習を進めていくと、あるテンポから鳴りきらないうちに次の音に移らなければならなくてその音は無音になります。
ここへきて「あれ?一つ前のテンポまでは出来ていたのに急に出来なくなった。テンポをひと目盛り戻してやってみても上手くいかない」ということになるのです。
ほんのちょっとの音量のばらつきやアーティキュレーションの正確さ、リズムのヨレ具合など、上手く行ってるかどうかの基準が精密かどうかというのは、意味のある練習ができるかどうかを左右します。
基準が甘いつもりはないのにそんなことが起きてしまう場合には、自分の演奏を吹きながら細部まで精密に聴けていないという証拠。
自分の演奏を脳内補正せずに客観的に聴く姿勢と、音のどこにどんな注意を払うかというソルフェージュ力は、練習の効率と精度を変えてしまいます。
あなたはどのレベルで出来たら次の段階に進む許可を自分に出していますか?
うっかりミスの取り扱い
練習していて、ちょっとした発音ミスや音間違えが起きた時にどうしていますか?
もしかして「今のは偶然だから忘れよう」なんて思っていないでしょうか。
どんなことにも必ず原因と結果があります。
ほんの小さなことでも、ミスが出たのなら何かキッカケがあったはず。
うっかりしたとか、準備不足なタイミングで吹き始めてしまったとか、色々あるでしょう。

ではそのキッカケが本番では絶対に出てこないと言い切ることは果たして出来るでしょうか。
油断した時に無意識でうっかりやってしまうことというのは、すでに習慣になっています。
ということは本番だってやる可能性がありますよね。
動作のために何を意図するかをあらかじめ考えるのは、大切な練習の要素です。
小さなうっかりを積み重ねつつ練習を進めていっても演奏の精度は上がりません。
偶然のようなうっかりミスが出た時にやりたいことは、なぜうっかりしたのかを考えること。
たまたま偶然うっかりするなんてありえないのです。
音を出すときに考えがちなことがうっかりミスを引き起こすなら、何を考えながら音を出すのか選択をする必要があるでしょう。
それからもう一つ、「何も考えずに吹いていた」というのは、何も考えずに吹くのが習慣になっているということ。
どんな音を出したいのかイメージを持たず、ただ無意味に音を垂れ流す。
本番でそんなことはしたくありませんよね。
何も考えなかったことがうっかりミスの原因だと気が付くことがあったなら、次は何か意図を持って音を出していきましょう。
いつ出来るかわからなくて焦る
ゆっくりテンポから練習しなければとは思いつつも、いつ出来るようになるのか見通しが立たない。
↓
練習時間があまり取れないから焦る。
↓
焦ってゆっくりテンポで出来てもいないのに速度を上げたくなる。
↓
当然ながら出来るようにならない。
おまけに崩れた音形の癖がついてしまって余計下手になった気がする。
↓
どんどん不安になってなおさらテンポを落とした丁寧な練習ができない。
ーーー
そんな無限ループを経験したことはありませんか?
出来るようになるまでの見通しが立てられるかどうかは、練習のモチベーションや心の状態に影響を及ぼすものです。
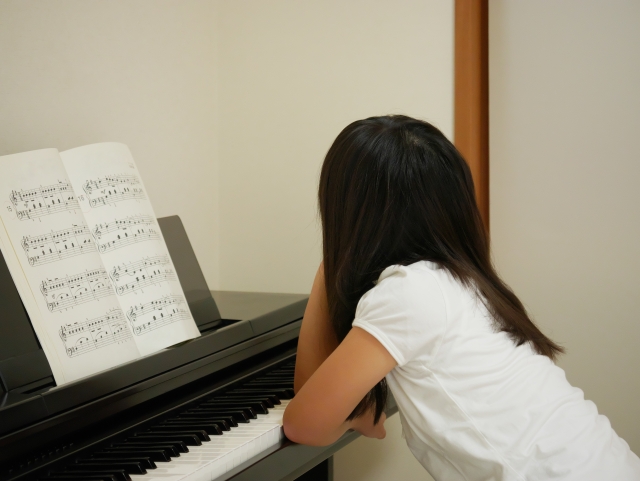
大変な仕事をしているときや人を待っているとき、トイレを我慢しているようなときに「後何日、何分がんばったら終わる!」という目安がわかればモチベーションも上がります。
ですが、「いつ終わるかわからないし、今がどんな段階かもわからない」という状況では、頑張れなくてイヤになったり諦めたりしてしまいがち。
そういう『今の自分では何の練習をどれくらい行うと効果が出るか』という目安がわかるのは、これまでに知識や経験を積み重ねてきたからこそ。
現状を把握するというのも、ひとつのスキルです。
初心者の状態で今後の見通しを知りたい場合には、やはりレッスンなどで専門家に尋ねるのが一番の近道でしょう。
ですが、続けていくに従って「この曲ならこんな手順で、これくらいさらう時間が必要だな」ということを考えてスケジュールを組んでいくことができるようになります。
「ヤバイヤバイ!まだ出来ない!」と常に焦りながら練習するのではなく、安心して段階を進めていくためには大切なスキルですね。
ゆっくり練習だけでは上達しない
「ゆっくりで音数の少ない曲や比較的簡単そうに見えるパートを選びたい」
初心者の頃にはそんな選択をしてしまうこともあるかもしれません。
玉砕覚悟で自分の実力以上に難しい曲に焦って取り組むのは、混乱する練習になってしまったり、思ったように演奏出来ない状態を自分の標準としてイメージを定着させてしまうことにもなりかねないのでおすすめできません。
とはいえ。
学校吹奏楽で演奏を始めた場合、本番が迫ってくる中でいきなりややこしいフレーズを吹かなければならないケースも少なくないでしょう。

そういう場合に何とかかんとか頑張っていると、いつの間にか上達していることもよくあります。
もがきながら一歩また一歩と先に進んでいくうちに無意識に課題をクリアしてレベルアップしていくという状態ですね。
自分の安心していられる場所から一歩抜け出したチャレンジを繰り返すと、そういう風にいつの間にか気付いたら上達していることにつながるのです。
もちろん最初は丁寧に基礎を積み上げて行く作業をした方が、後々出来ることが増えたり応用範囲が広がったりします。
ですが、
「自分はまだ初心者だから」
「今は他のことが忙しいし」
など言い訳をして新しいチャレンジをしなければ、いつまでも経っても初心者のまま。
丁寧に進めることと初心者状態に甘んじ続けることはイコールではありません。
例えば
・昨日より一目盛りだけ速いテンポで吹いてみる
・ソロの人がお休みしたらそのパートを補って代奏してみる
こんなことも一歩進んだチャレンジと言えるでしょう。
きちんと土台を積み上げつつ前に進む作業も意識的に行なっていくことは上達のためには必須です。
それは玉砕覚悟の無謀なチャレンジをすることではなく、安全圏から一歩外れたトライを行う習慣を持つということ。
習慣的にチャレンジを続けた人はどんどん新しい世界を知っていくので、それに伴って目標となるビジョンもどんどん明確になり、さらに上達していきます。
「決まった手順はきちんとこなしているけれどなかなか上手くなった手応えがない」
そんな場合はただのルーティンに陥ってチャレンジのないことを繰り返していないかどうか、振り返ってみるのも良いかもしれませんね。
「面倒くさい」に勝てるかどうか
「適切な手順を踏んだ丁寧な練習をするとやはり上手くはいくけれど、時間がかかるから新曲に出会う度に毎回はできない。」
そんな声をたまに耳にします。
確かに、
・急いで譜読みをしなければならない
・練習に時間があまり取れない
そんなときには、気が焦っているので丁寧に楽曲に向き合うことは難しいでしょう。
完成度には拘らずにテンポを上げてしまった方が早く「出来上がり」に近づく気がするかもしれません。
でも。
適切な手順を踏んだ丁寧な練習を取り入れようと思ったのはなぜですか?
これまでの練習手順では出来ないことや不十分なことがあったからではないでしょうか。
仕上がりが不十分で雑な出来になるとわかっている方法でいくら早く仕上がったって、結局は不満と後悔が残るでしょう。

新しく取り入れる段階で『丁寧な練習』が面倒くさいのは当然です。
脳の回路がまだ慣れていないのですから。
慣れていないことには時間がかかる。
そして取り掛かるのに抵抗を感じる。
それは自然な反応です。
つまり今のあなたにとって、新しい丁寧な練習よりも今までのやり方のほうが慣れているというだけのこと。
新しい丁寧な練習の方が今までのものよりも慣れている、という状況にするのは根気強い繰り返しの選択が必要です。
「面倒くさいな」
「手っ取り早く済ませたい」
「満足できなくてもそこそこの出来でも良いか」
そんな気持ちになった時こそ、再選択のチャンスです。
あなたは「面倒くさい」を乗り越えて良い奏法や表現に近づきますか?
それとも今まで通り手っ取り早く済ませては後悔を繰り返しますか?
優秀な人の共通点
演奏現場やレッスンや講習会で、驚くような技術の高さと魅力的な音楽をお持ちの方に出会うことが多々あります。
どうしたらそんな風になれるかなど簡単に言えるわけもありませんが、見ていて接してみて一つだけそんな人に共通のことがあると感じました。
それは優秀で上手な人ほど自分に対して客観的な視点を持っているということ。
・自分に必要なことは何か
・提供されたアイデアが今後の助けになるのかどうか
目をそらしたり虚勢を張って自分をごまかすのでなくきちんと見ることが出来て、どんなことからもどんな相手からも謙虚に学ぼうとされるのです。
そしてそれは自己肯定感の低さから卑屈になるケースの反対で、自分の足りないところを正面から見つめたとしても壊滅的なダメージを受けたりしないという自信があるからこそできるのではないでしょうか。

優秀だからこそ客観的になれて学びの機会をキャッチ出来るし、学びの機会を逃さないからこそ優秀になったのかもしれませんね。
反対に周りをよく聴いてなかったり謙虚に学ぶ姿勢のない人ほど、自分に自信を持ってるようでいて実は自分の欠点や足りないことを自覚するのを恐れているように感じます。
自分を守るために他人を攻撃したり、肯定してくれる人だけを側に置いたりする、というのは人生単位で損ですね。
ということで、わたしはレッスンに来て下さる方、特に年上のプレーヤーさんたちはプロアマ問わず本当に素敵な人ばかりだなと感じるのです。
わたし自身も年下や後輩という謙虚になりにくいけれど本当は尊敬できる相手に対したとき、そう振る舞っているかどうか振り返ってみたいなと思います。



