楽器を吹くことに夢中になって見落としがちですが、「表現する」とはどういうことなのかきちんと把握するのも演奏力の向上には必要です。
今回は表現することについて、考えさせられる興味深い書籍をいくつかピックアップしてご紹介します。
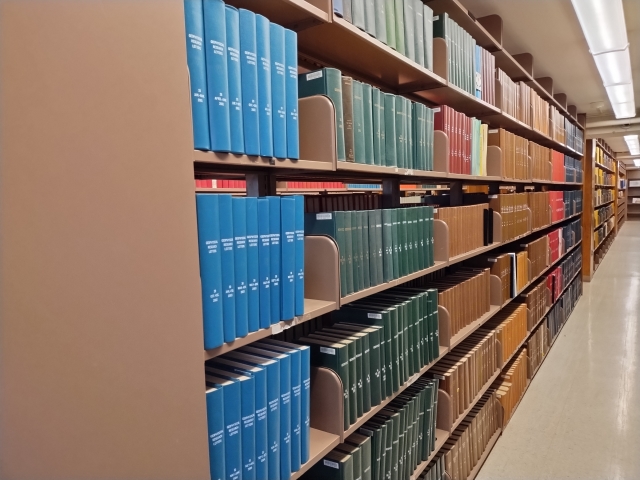
ただ聴くだけのことが難しい
文芸評論家であり作家でもある小林秀雄さんの著書「考えるヒント3」に収録されてる「美を求める心」というエッセイ、ある新聞で紹介されていたのを見かけて読んでみました。
ほんの10ページほどの短いエッセイです。
一文一文ハッとさせられるようなものばかりでしたが、その中でも特に印象深かったのはこんなことでした。
「美しさを感じる心というのは分析理解することでなく、対象そのものを愛し感じることでぼんやり見ずに繊細に感じることは訓練が必要である。」
「大人になると花を見ても名前を認識できたらもう花は見ない。こどもは花の名前は知らなくても微妙な色彩や形をいつまでも飽きずに眺めている、 それが美を感じること」
指揮者のフルトフェングラーも自身の著書で音楽について同じことを述べてます。
これは美しさというのは何かという話ではなくて、音楽や詩・絵画を「わかろうとする」人に向けて書かれた文章のよう。
わかろうとすることと感じようとすることの違い、深いですね。
私はよく和音やフレーズがどんな印象だか言葉にしましょうと発信しています。
名前をつけたり分析したりせずにただ感じることが大切だ、というこのエッセイの著者とは言葉上は反対の理論のようですが、音楽に限らず芸術を楽しみたければ感覚を研ぎ澄まして繊細な違いに目が向くように訓練する必要があるという点で全く矛盾するところがなく共感できると感じます。
また、「ゴッホの絵を理解しようとする時に『ひまわりだ』と名前がわかったらもうそれをわかった気になって味わわない、それはもったいない」という言葉も印象的でした。
普段はオケ曲ばかり演奏する人がふとジャズライブを聴いた時のような、不慣れで詳しくないことに接する場面。
そんな時に、どうしたらいいかわからなくなってしまうことは多いのではないでしょうか?

例えば普段クラシックしか演奏しない人にとっては、ジャズは意味不明でどこをどう楽しんだらいいかわからないかもしれません。
アドリブ音楽を専門にする方は、クラシックのニュアンス変化やゆらぎには不慣れだったりするでしょう。
結局わからないものは自分の知っている方法でしか触れられない、ということかもしれませんね。
それは知らないジャンルだけでなく絵画や彫刻など異分野のものも同じことが言えるでしょう。
知らないし慣れていないジャンルは、理解しようとしても理解の仕方がわからないのですから、わかろうとして触れるのはムダかもしれませんね。
小林秀雄さんのエッセイではさらに、「わかろうとせずただ味わう」ということがいかに大切で、また難しいかということが書かれています。
良い悪いを判断しようとしたり、何がどうなってるか分析したりということではなく、ただ聴く・ただ触れる。
そのときに自分の感覚や気持ちがどんな風に動くか、ただ観察をするというのは面白いものです。
これはボンヤリ流し見する・聴き流すのとは全然反対のことでしょう。
そういう姿勢で作品や演奏に触れると、「チャイコフスキーは好きだけどシェーンベルクはよくわからないから嫌い」などの単純で表面的な判断によって拒否してしまうことが減るのではないでしょうか。
その方がずっと楽しめることが増えていくので、きっと人生が何倍も面白くなるでしょうね。
他にもロシア文学についての考察、表現することについてなどなど、興味深いテーマでいくつもエッセイが収録されています。
普段つい目先の手軽な満足感を追いかけてばかりになってしまう、そんな方にとてもオススメです。

「考えるヒント3」
小林 秀雄著
文春文庫より
スコアリーディング
次は「スコアを読んでみたいけど何にもわからないからどこから手を付けたらいいのか・・」という方におすすめな本をご紹介します。
実際のポケットスコアみたいな見た目がなんだかかわいいですね!
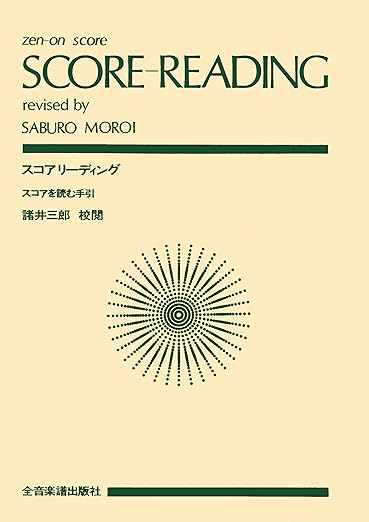
著者の諸井三郎さんは楽曲解説などでかなり鋭く的確な文章を綴られる方なので、気になっており買ってみました。
内容は楽曲解説の導入というよりはかなり優しいオーケストラのスコアを読むための導入、というイメージ。
むしろスコアの「読み方」というより、「眺め方」といった方が適切なくらい初めての方向けかもしれません。
基本的な楽典や和声、アナリーゼの知識がある方にとっては物足りないと思いますが、合奏経験があまりなくオーケストラに入団したばかりで「取り組んでいる曲のスコアを買ったけれど使い方がわからない」という方には役立ちそうです。
中身をざっくりとご紹介すると、
・楽器の表記や特性について
・ト音へ音ハ音など各音部記号と移調楽器について
・実際の作品での例
という構成で50ページほどしかなく、あっという間に読めてしまいます。
「パート譜はいつも見ているけどスコアは何だか難しそう」
「よく見かけるけど読めないこの楽器はなに?」
「移調楽器ってどういうものなの?」
というような誰に尋ねたらいいかわからないような基本的なことについての疑問が解決します。
楽典よりはるかに薄いですし、シンプルで簡単な導入を求めている方にピッタリかもしれませんね!
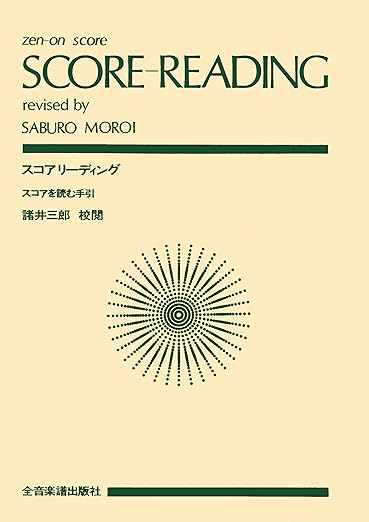
スコアリーディング
諸井三郎 著
全音楽譜出版社
棒読み演奏になる日本人ならではの原因
この本はおすすめというわけではありませんが、興味深い記述があったのでその部分をざっくりとシェアしたいと思います。
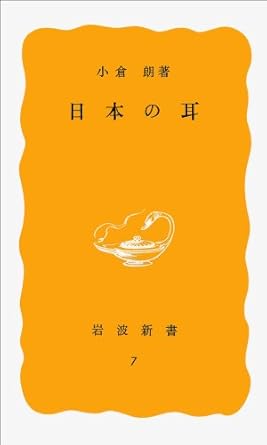
日本の耳
小倉朗著
岩波新書
全体としては言語や身体機能、また文化や歴史などから演奏を考える内容になっています。
その中で印象的だったのは日本の昔からの音楽と表現方法についてのところ。
平安などの昔から、武士や貴族と庶民の音楽は違っていました。
・武士や貴族の音楽は高低の抑揚ではなく強弱の抑揚がメインであり、庶民の音楽は強弱ではなく高低の抑揚がメインだった。
・高低の抑揚が制限されると必然的に一本調子のように感じられる。
・武士や貴族は感情を露わにすることを制限することが美徳とされていた。
ということが述べられています。
思い切ってわかりやすく分類してしまうなら、一本調子の音楽は高貴で、情感豊かな表現は低俗、と考えられてきたと言えるかもしれません。
このあたりの記述を読んで、今日わたしたち楽器奏者が人前に出た時に一本調子の棒吹きになってしまいがちなのは、それが一つの要因になっているかも知らないと感じたのです。
というのは、ステージなどの「公の場」では無意識に
「みっともないところを披露せず自分を律さねば」
「人前ではかしこまった様子にするべきで感情を露わにするような下品なことはしてはならぬ」
という思いが心の片隅に潜んでいるから。
もしかしたら自宅だったり、気を許せる仲間だけのときには、何の遠慮もなく感情豊かな振る舞いを出来るのではありませんか?
それが人前に立った途端に出来なくなるというのは、文化的歴史的な側面が影響しているのかもしれません。
そういう傾向があると知っていれば、ステージという「公の場」で思い切って「私的な」振る舞いをするためにどのように気持ちの整理をする必要があるのか考えることができますね。
大変興味深い記述だったのでご紹介しました。
少々読みにくい部分のある本なので敢えておすすめはしませんが、もし興味の湧いた方は手に取ってみても面白いかもしれません。
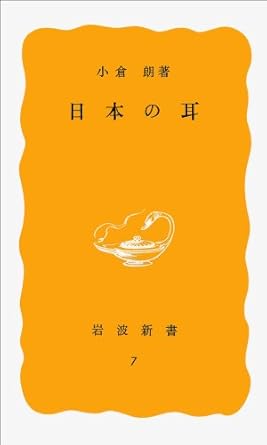
日本の耳
小倉朗著
岩波新書



