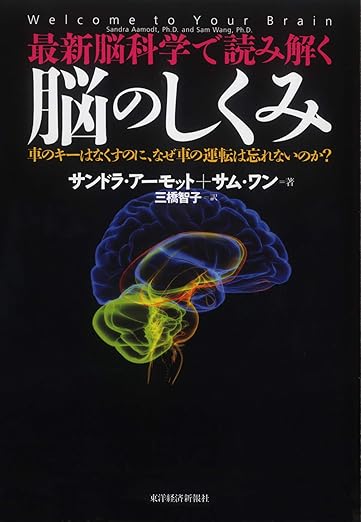脳の仕組みについての本で、音楽やスポーツなど練習が必要な分野では参考になることがたくさんのものがあったので、いくつか印象的だったことを引用しつつご紹介します。
「最新脳科学で読み解く脳のしくみ」
サンドラ・アーモット、サム・ワン 共著
東洋経済新報社より
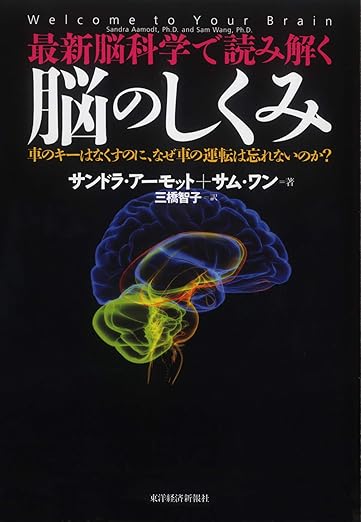
トラウマもイメトレも同じ仕組み
まず興味深いなと思ったのは
「ある記憶を意図的に強化するのも、つい悪いことを予測してしまうのも、結局脳では同じことが起きている。」
ということ。
俳優さんやスポーツ選手が望む結果を何度もイメージするのは、脳の中に強い心的イメージを生み出す役に立つということが例に挙げられています。
いわゆるイメトレで良い結果に結びつけるのも、「悪いことが起こるのではないか、失敗するのではないか」と思い続けた結果それを引き寄せて失敗するのも、同じことなのだそう。
そして過去の悪いことを繰り返し思い出すと、トラウマを作り出すそうです。
考えてみると恐ろしいですが、辛いこと悲しいことをつい思い出してしまうのは自分の努力不足などのせいではなく、出来事の強烈さによる当たり前の反応だとか。
だからトラウマを消す治療としては、それが思い浮かんだら違うことをするように決めておく(手首に巻いておいたゴムを引っ張る、身近な人に指摘してもらって話を変える、など)ことが有効だそう。

手首のゴムなどは些細なことですが、きっとその辛い記憶と無関係であることが大切なのでしょう。
ブレスレットのビーズの数をかぞえるなども良いかもしれませんね。
また例えばコンサートの本番で失敗てしまったことが忘れられずたびたび思い出すなら、次にそうならないために何ができるかを建設的に考える、というのも役に立つそうです。
次に、「ストレスを受けた時に出るホルモンは学習効率を上げる。慢性ストレスは脳を傷付け逆に学習効率や記憶力を下げる」ということも書かれていました。
「なにくそ!」と思ったときに上達する人がいるのはそれですね。
とはいえ自己否定をし続ければ慢性的にストレス状態になるので上達はしにくいということ。
音大出身者やアマチュアでも真剣に音楽に向き合って来た方には共感することかもしれません。
「自分は劣っている」という自意識を燃料にしてこれまでやってきたけれど、あるときからその燃料では稼働できなくなったり、心が疲れ果ててしまうなどはこういう仕組みなのですね。
苦手は思い込みが作っている
次に興味深かったのは、思い込みについて。
動作や行動で何かするときに「これは楽しい!好きだ!」と思う場合と「なんか不快だな。キライかも。」と思う場合があるでしょう。
ある人は歌をうたうと楽しいし良い気分になるから好きだといいます。
別の人は歌は好きじゃないし歌っても楽しい気分になるどころかなんだか居心地悪く感じてしまう。

その違いというのは、歌をうたうということ自体ではなく、歌っている時の身体の状態によるそうです。
これはアレクサンダーテクニークの原理発見者であるF.M.アレクサンダーさんのいくつかの著書でも述べられていて、興味深く感じたポイントでした。
もちろん好き嫌いの条件はそれだけではなく他にもたくさんあるでしょうが、考えてみるとその通りな面も大いにありますよね。
自分自身を観察してみても、好きなことをしている時は伸びやかな気分で身体の動きもたくさん起きているのに対して、キライなことをしている時はやはり少し動きが硬くなることに気づきます。
「好きだ!楽しい!」
「苦手だし避けたい・・」
その思いが、身体の動きの質を決定づけることもあるのでしょう。
しかしその要素が逆に働くこともあるそうです。
たまたま初めて歌ってみるときに、風邪を引いていて体調不良だったら?キライな人がそばにいる状況だったら?
その場合は、歌とは関係なく身体の動きは少し不自由であり、それが「歌は苦手だ」という思い込みを作ってしまうことも考えられるのだそう。
実はそういうケースは結構あるかもしれません。
好きな人や尊敬する人が勧めたら何でも素敵に感じるし、キライな人が勧めるものは何だろうと嫌に感じたりします。
演奏の場面で考えてみると、曲の中で「吹きにくいな」「ここは苦手だな」と思う部分があったとしても、それは気持ちが身構えてしまうために自分で身体を固めて不自由な状況を作り出しているのかもしれません。
それなら本当に苦手だったり自分にとって困難な動作であるという事実と、苦手だと思い込んでいるために身体を不自由にしてしまっているケースは分けて考える必要があるでしょう。
わたしたちは何かを判断したり感じたりするということは、純粋に思考や感情に関わると思いがち。
でも実は自分で作り出してる身体の動きから、思考は大きな影響を受けている。
とても興味深いことだなと思ったのでした。
なんとなく苦手でやりにくいなと感じる箇所では、自分で身体を固めてしまってはいないか、無意識に呼吸を浅くしていないか、など振り返ってみるのも良いかもしれませんね!
性格は習慣で変わる
もう一つ、すごく納得したのが「何かをすると決断した、という自覚よりも前に脳は活動を開始している」ということ。
意識的にわたしたちが何かを決断をする前に、脳はすでに勝手に決断しているんだとか。
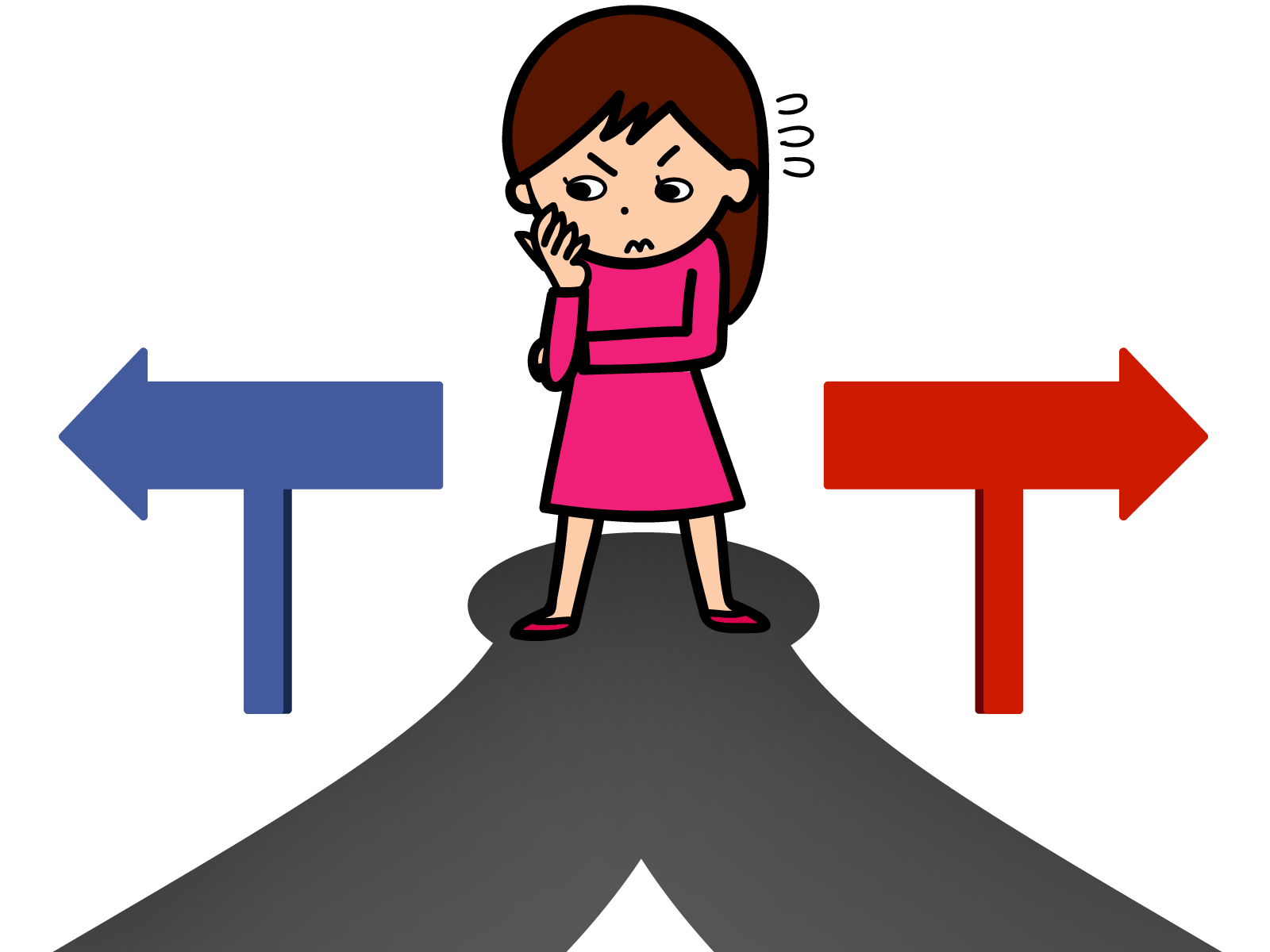
確かに決断をするまでに色々な葛藤を乗り越えている時間、それはすでに決断に向けて心を整理している状態と言えるかもしれませんよね。
電極で調べても人は決断をする前に決断の信号をすでに発しているそうです。
そして決断も練習などの作業も同じで繰り返すほど慣れていって、新しいものに飛び込む癖のある人は常に飛び込み続けるし、逆にやらないことに慣れている人は渋るのが当たり前になっていく、とも。
だから生産的な人とそうでない人のIQだとか学生時代の成績だとかはあまり関係なく、どういうものを意図的に選ぶ習慣があるかで人生と性格が方向付けられるそうです。
わたしたちは日常でつい楽な方に流れがちではありますが、何を楽と感じるかはそれぞれ。
落ち着きのない人は落ち着いていられないからこそ新しいことをするばかりで一つ一つが深まらないけれど、新しいことをしない人はそれはそれで発展性がないなど。
考えさせられますね。
自分がどういう傾向を持ってるのかは知っておいて損はないと思います。
また「脳の仕組みを使うために、仕組みを知っている必要はない」というのはまた頼もしいお言葉。
車を運転するのに車を作れる必要がないのと一緒ですね。
脳のことはまだまだ未解明のことも多くて、これから明らかになるだろうこともたくさんなのだそうです。
未知のことを知って生活に活かせるようにアレンジしていくのは楽しいことですね!
おわりに
そして最後に。
わたしはこの本を読んで印象的でなかった大部分は2日ほどできれいさっぱり忘れました。
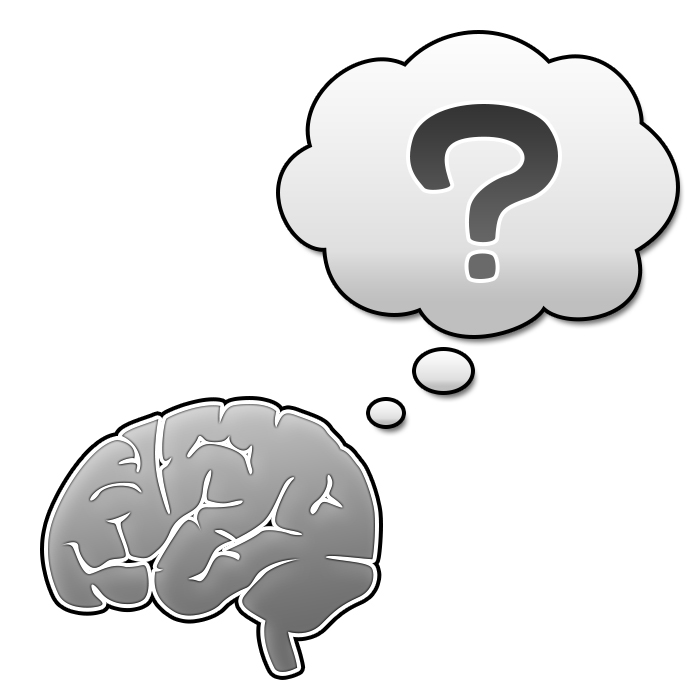
だからわたしが印象的だったと紹介してる内容は多分に偏っていると思います。
自分の専門に直接関わらないと思うと長期記憶に残るところまで行かないのでしょう。
そして情報の洪水の中で自分にとって必要な情報を取捨選択していくのも脳の働きなんだとか。
ばっちり作用してくれているようです。
何もかも覚えていたら逆に引き出しが多すぎて適切なときに適切な情報を引き出せなくなるわけで、ありがたい機能がたくさん備わっているということですね。
とても面白ったのでオススメです。
気になる方はこちらからどうぞ
▼▼▼
「最新脳科学で読み解く脳のしくみ」
サンドラ・アーモット、サム・ワン 共著
東洋経済新報社より