演奏は聴いてくれる人無しには成り立ちません。
それなのにお客さまとの関わり方を考えている奏者はそう多くないという現実。
義理でコンサートを聴きに来てもらえるのはせいぜい2回まで。
演奏者もお客さまも楽しめるよう、双方向のコミュニケーションを工夫したいものです。
今回はコンサートを行う上で、考えておきたいお客さまとの関わりについて考えてみました。
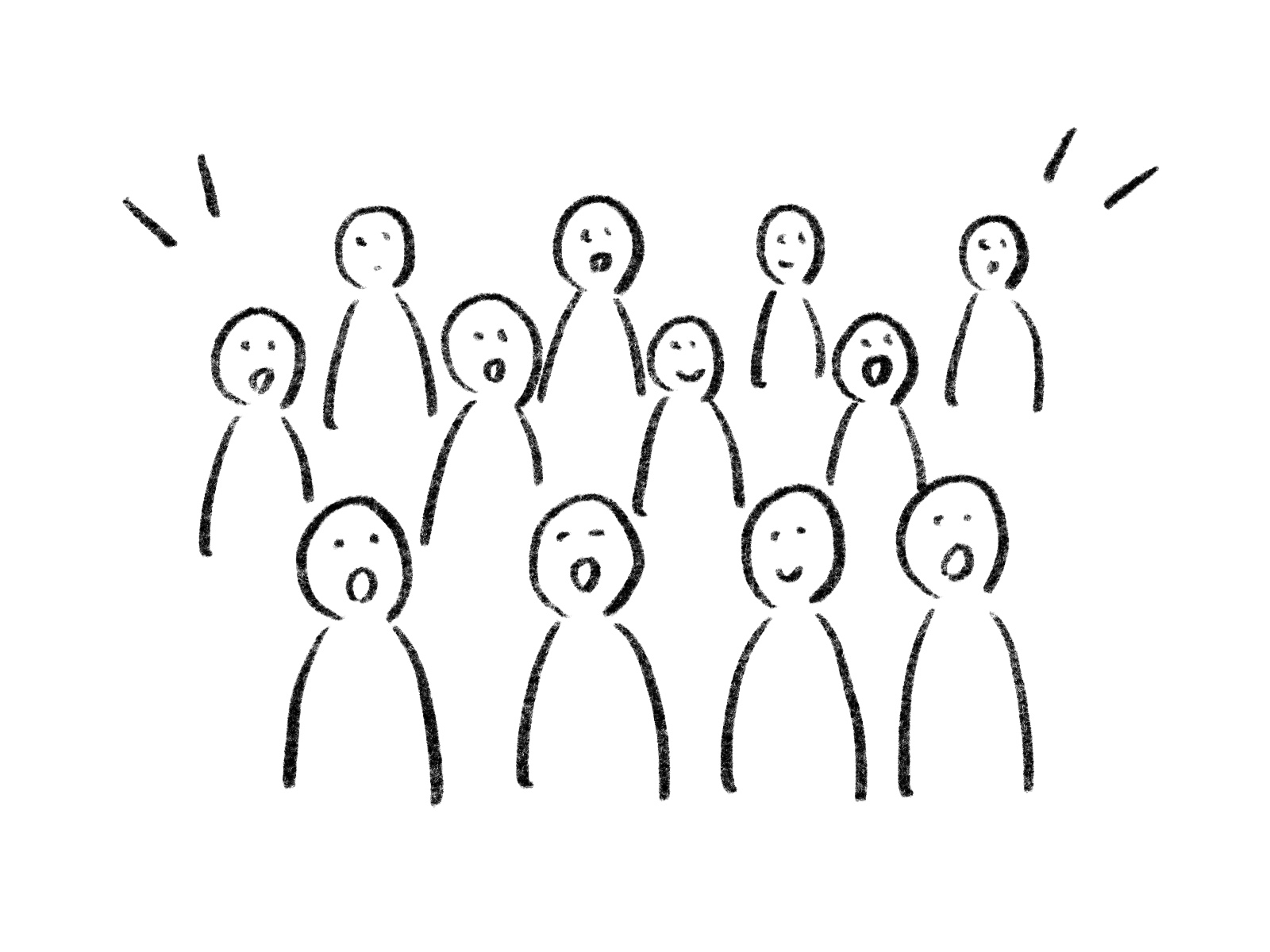
ファミリーコンサートのプログラミング
「ファミリーコンサート」などのタイトルで演奏するプログラムに、前半はクラシックで後半はポップスという組み方をよく見かけます。
でもこれ、「まずはわたしの話を聞いて!その後であなたの話を聞きます」と言っているようなものではないでしょうか。
まずは相手の目線に立って、相手に不安なく居心地よく感じてもらってこそ、こちらの話に耳を傾けてもらえるのではないでしょうか。
「知っている曲だ!大丈夫、音楽は難しくない!」
そう感じてもらえたら、解説しつつ近現代の無伴奏作品を取り上げても意外に面白く聴いてもらうことができるものです。

演奏する側は事前にしっかり準備してドキドキしながらクラシックの名作に取り組むので、「早いうちに真剣な曲は終わらせて後半はポップスで気楽に吹きたい」そんな風に思うのかもしれません。
でもそんなのは演奏者の都合です。
普段は音楽に親しみのない方が初めて耳にする曲が気合いの入った大作だったら、びっくりしてしまうかもしれないし「やっぱり音楽はわからない」と心を閉ざしてしまう可能性だってあるでしょう。
オーケストラだって前プロは短めに導入して、心の準備ができた後半でメインの長大な作品を取り上げることがほとんどです。
いきなり90分のシンフォニー、そして後半に小品がたくさんだったら聴く側としてどうでしょう?
前半に疲れてしまい、後半のプログラムには興味を持てないかもしれません。
たとえば吹奏楽の定期演奏会として、あまり音楽に興味のない親族やお友達メインのライトな客層を想定していた場合。
飽きない内にと前半にクラシックステージ、飽きてしまった後半にポップスという組み方の意図はよくわかります。
しかし後半に飽きてしまうのは、準備運動も無しにいきなり慣れないクラシックを聴かせて疲れさせるからかもしれませんよ。
相手に届きやすい構成を考える、それはコンサート準備の大切な要素の一つです。
ウケる曲だけ選んでいませんか?
「今日は音楽に馴染みのないお客さんが多いから知っていそうな曲を取り上げよう」
そんな場面はきっと少なくないでしょう。
相手の目線で聴きやすいものを選ぶというのは大切です。
とはいえせっかく生の演奏を聴くなら、知っているものだけでなく知らなかった作品や音楽の新しい魅力にも触れてもらいたいもの。
あなた自身を振り返ってみると、どうでしょうか。
専門外のことだったけれど良さとか触れ方をわかりやすく教えてもらえたら意外に楽しくてハマってしまった、そんな経験はないでしょうか。
料理人が使ってる秘密の裏ワザとか、ライフハック的な収納術とか、興味は別になかったことでも流し見していたテレビでやっていたら見てしまうかもしれません。

そんな風に自分の専門外のことでも、知ってみたら結構面白かったり「試してみよう!」と思うことって意外にあります。
同じことでせっかくコンサートに足を運んでいただくなら、新しい作品も織り込んで音楽に触れる楽しさをより深めていただきたいもの。
そのためには奏者としても自分たちが演奏したい曲を寄せ集めるのではなく、意図を持ったプログラムを考える必要があるでしょう。
聴く立場としては知らない会場で知らない曲をいきなりたくさん押し付けられても楽しむのは難しいでしょうから、やはり馴染みやすい曲を演奏してくれるという安心感が先にあると敷居を低く感じてもらいやすいもの。
そう考えると、もしかしたらポピュラーな曲を交えたプログラムを組める機会は知らなかった曲を紹介するにはぴったりな場面かもしれませんね。
また、MCをわかりやすく工夫するのもコンサートを組み立てる上で大切な要素のひとつ。
簡単に聴きどころをコメントしたり解説をつけたらより楽しく聴けますし、新しい曲にも不安なく触れられるでしょう。
「あなたが知っていたさっきの曲とはこんなところが違って、そこが魅力です」
「ここに注意して聴いてみると面白いですよ」
「わたしはこの曲のここが好きで今回取り上げました」
そんな風に紹介してもらえたら知らない曲だって結構楽しく聴けるもの。
ただ知っている曲やウケやすい大道ものだけでは、安心感はあっても新しいものに触れるワクワク感はないでしょう。
知ってるものを聴くのも楽しいけれど、せっかくなら「音楽っておもしろいな、もっと知りたいな」という気持ちで帰ってもらうことを考える。
その方が、ただの自己満足よりも意義のある演奏になるのではないでしょうか。
演奏するなら聴いてくれる人が元気になったりワクワクを持って帰って貰える方法も考えて行きたいものですね。
近現代作品はつまらない?
この頃ちょこちょこCDの伴奏で演奏する機会があります。
クラリネットはアンサンブル楽器なので全くの無伴奏ではあまり演奏しません。
1本で演奏して欲しいとなったらヴァイオリンやチェロ、フルートなどの無伴奏作品を取り上げたり、クラリネットのオリジナルなら近現代の作品を取り上げることになります。
とはいえ、近現代の無伴奏ソロの作品は調性も拍子も無いようなものが多いので、リサイタルやコンクールなどではない商店街のイベントのような場面ではなかなか演奏されないのです。

そういう無調無拍子無伴奏の作品は誰かのリサイタルに出かけて行って「よし!クラシックを聴くぞ!」という心づもりのお客さんには楽しんでいただけるでしょう。
しかし休日お買い物ついでの通りすがりに「音がするから立ち止まってみようかな?」というテンションのお客さんが楽しむのには少し敷居が高いかもしれません。
「音楽といえばアイドルの歌」、というイメージを持ってる人にいきなり《現代曲を聴きましょう》というのは普通に考えてちょっと無理がありますから。
そういう方にも近現代作品を楽しんでもらったり、「今度はコンサートホールにも出かけてみようかな?」と思ってもらうにはどうしたらいいのでしょうか。
これはコミュニケーションのお話です。
誰でも2才の日本人の子供にロシア語で哲学の話を振ったりはしないと思います。
相手が子供なら理解できるように簡単な言葉を選ぶでしょうし、お互いに通じる話題を選びます。
そしてお互いに「この相手との会話は安全である」と思えてから、「ところで」と新たなトピックを持ち出してみるのではないでしょうか。
コンサートのプログラムも一緒です。
「知っている」「懐かしい」「今話題のフレーズだ」という安心感が先にあったら、そのコンサートを楽しいと感じ始めるでしょう。
その信頼関係が出来てから「実はこんな作品もありますよ」と紹介する。
《聴くのが楽しいモード》になっていれば、紹介された近現代作品も「へー!知らなかったけれど面白い!」という反応をしやすいでしょう。
「この奏者を追いかけてみたら新しい世界を見せてもらえるかも!」そんな風に思ってもらえたら大成功。
知らない曲が並んだリサイタルでも「試しに行ってみようかな」と思ってもらえるかもしれません。
反対に知っている曲や懐かしい作品に終始してしてしまえば「あー懐かしかった」で終わってしまいます。
この奏者の演奏をさらに聴いてみたいと期待を持つどころか、「早く帰ってYouTubeで懐かしい曲をもっと検索してみよう」と思うだけかもしれません。
人間の感じる楽しさは「知っていること・安心であること」だけではなく、知らないことに出会うという冒険やワクワクも大きな要素です。
知らない曲だけを押し付けるのは独りよがりだし、知っている安心感ばかりを頼るのも安易すぎるでしょう。
演奏者としては演奏の質の向上だけではなく、お客さんとのコミュニケーションも大切にしていきたいものですね。
つまらないMCにはうんざり
演奏前のMCでつまらいないのは
「これから演奏する曲はきっと聴いたことのあるフレーズなので楽しんでいただけるのではないかと思います」
「これは何年にどこで誰が作った曲です」
「全体が緩ー急ー緩になっていて、ソナタ形式でこんな進行で・・・」
というような内容のコメント。
個人的にはこういうMCは全然面白くないし、その後の演奏への期待が高まることもありません。
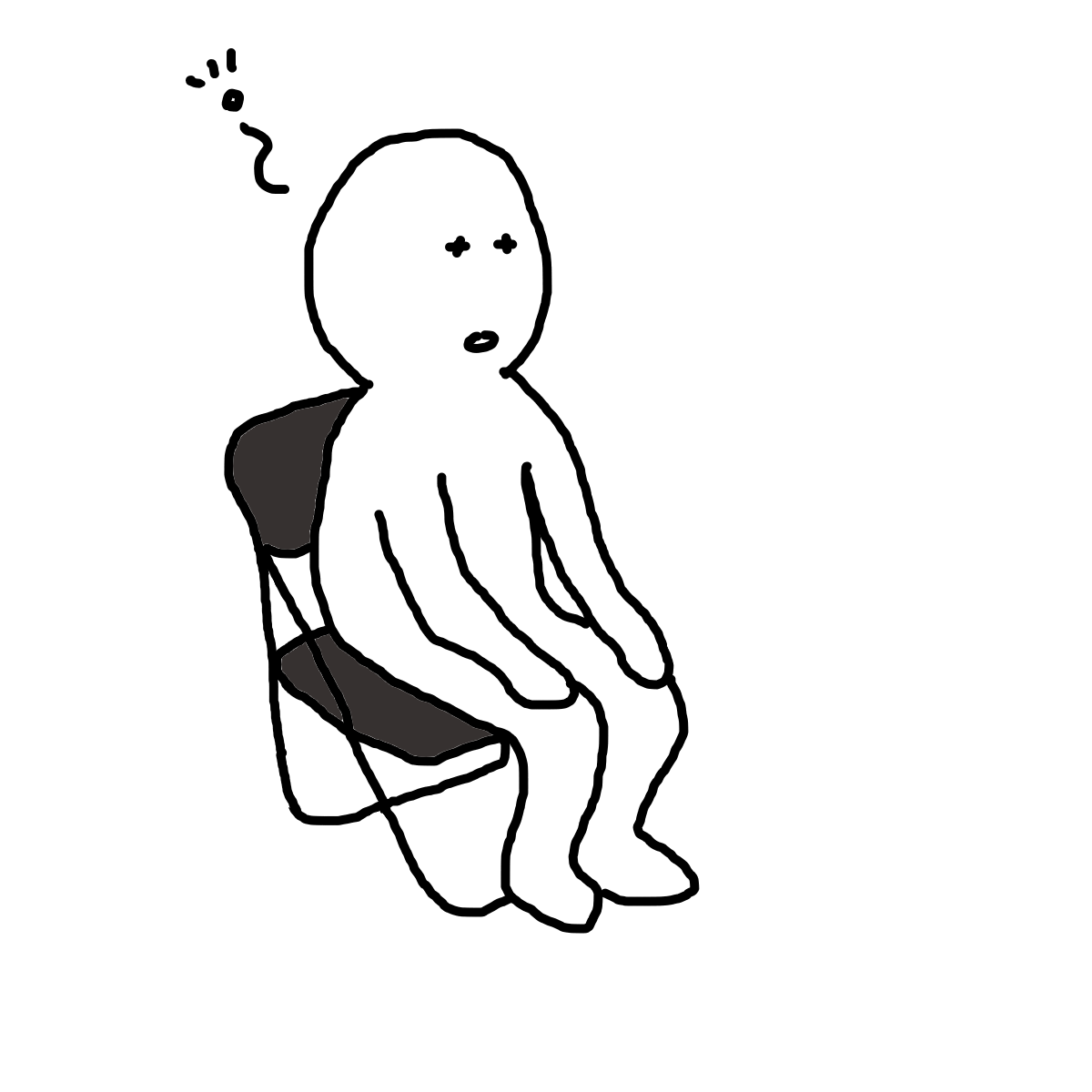
コンサートを聴きに来たのは知っている曲で安心するためではないし、音楽史の勉強をするためでもない、楽曲分析の解説を知りたくて来たのでもありませんから。
知っている曲を取り上げること自体は、相手の目線で聴きやすいものから導入するという姿勢であり大切です。
でも何度もテレビで観てストーリーも全部知っている旧作水戸黄門のために、遠くの映画館に足を運ぶことはないでしょう。
俳優さんが舞台挨拶に来るとか、シリーズの新作が公開されたとか、懐かしのバージョンがリバイバルされるとか、そういう「今ここ」である必要を感じるからこそ、わざわざ出かけていくのです。
演奏を聴きに来てくれているお客さんは、あなたが演奏する「知っている曲」を敢えて今ここでどう楽しめる可能性があるのでしょう?
「知っている」=「楽しめる」
だと安易に決めつけるのは失礼かもしれませんね。
また、「何年にどこで誰が作った」とか「構成はこうなっていて」などの、講義のようなMCも魅力的とは言い難いでしょう。
知らない人にとってはピンとこないし、知っている人にとっては当たり前な内容であり、事前に知りたければ行きの電車の中で暇つぶしにスマホで検索でもすればすぐにわかります。
お客さんはそんなことを聴きに来たのではないでしょう。
逆に、
・その作品をなぜ取り上げたいと思ったのか
・奏者自身はどの部分が魅力的だと思っているのか
・ここでしか知れない裏話
などは面白いかも知れません。
わざわざ出かけようと思ってくれるほど演奏者に興味を持ってくださるお客さんにとっては、特に奏者がどんな思い入れを持ってこの曲に取り組んできたかというお話は、きっと気になるでしょう。
私たち演奏者は演奏がメインでありおしゃべりのプロではありません。
芸人さんやアナウンサーのように上手に話せる必要はないでしょう。
それでもMCというのはそれを専門の仕事にする人がいるくらい奥深いもので、何でもいいから声を出しさえすればいいという「添え物」でもないはず。
原稿なしのアドリブお喋りの方がライブ感が出て良いと言う人もいるかも知れませんが、「何を話そうかな・・」というその場しのぎのつまらない雑談や調べればすぐにわかるような「講義」は貴重な時間を使って聴きたくないのです。
コンサートが楽しかったかどうかは演奏だけではなく、全体の流れがどうだったかも関係するもの。
雑なMCでお茶を濁すような、聴く人に時間の浪費をさせる行為は失礼です。
その場で即興で言いたいことをまとめる自信がないのなら、事前に何を話すか考えておくくらいの準備はするのが当然というもの。
演奏だけでなく、コンサートに関わるすべての要素に気を配れたら良いですね!
お客さん放置で奏者だけ楽しむ
音楽は演奏する人の方が、聴く人の何倍もワクワクドキドキして楽しんでいます。
それは自分が何かを発する「自分ごと」であり、言いたいこと聴いてもらえる貴重な機会だからなのかもしれません。
きっと演奏者でもあり、誰かのコンサートに足を運んだ経験もある方なら頷けることでしょう。
演奏する時にはアドレナリンが出ていて心も身体も《パフォーマンスモード》になっており、休日にビール片手にカウチポテトをしている状態とは全く違っています。

しかしクラシック音楽のコンサート会場でお客さんはどうしても「参加している」というよりも「傍観している」立場になってしまいがち。
せっかく時間を作って会場まで足を運んでくれたお客さんは置いてきぼりで奏者だけが音楽を楽しむ、そんなことがあって良いわけがありません。
こんな言葉を知っていますか?
三流のパフォーマーは自分たちだけ楽しみお客さんは退屈する。
二流のパフォーマーは自分たちもお客さんも楽しめる。
一流のパフォーマーは自分は退屈してもお客さんを楽しませる。
もちろん必ずしも演奏者が退屈する必要はありませんが、演奏者の状態を優先してお客さんが放ったらかしでは、それは仕事とはいえないでしょう。
ポピュラー音楽では一緒に踊ったり、演者からの呼びかけにリアクションとして声を出せたり、ペンライトで会場に彩りを添える機会があったりなど「参加している」状態を作る工夫がたくさん見られます。
とはいえクラシックのコンサートでそれをそのまま導入するわけにはいきません。
それでも工夫次第でお客さんにも参加する楽しさを味わっていただくことはできるはず。
たとえば「ここに注意して聴いてみると面白いですよ」というような聴く時の着目ポイントを事前に伝えるのは一つのアイデアです。
わかりやすい音量の大小でも良いでしょうし、ソルフェージュ力のある程度期待できるお客さんなら明るい和音と翳りのある和音の聴き分けを提案するのも面白いかも知れません。
和音の色彩を色で思い浮かべてみたり、場面ごとに最低音を出している奏者が誰なのか探してみたり、拍子に合わせて心の中で指揮をしてみたりもできるでしょう。
子供向けコンサートなどであれば似たフレーズが何回出てくるか数えたり、特定の奏者と一緒にブレスしてみたりなど遊びの要素があっても楽しいですね。
せっかくなら一緒に楽しめるよう、そういう聴き方のヒントを提案するのもMCありのコンサートならではの魅力です。
そんなMCが付くなら、初めて聴く作品や難解な作品でも「参加している」という気持ちを持つことができるかも知れません。
来てくれたお客さんが帰り道で「面倒だったけど呼ばれたから仕方なく義理を果たした」と思ってしまうのは悲しいこと。
「面白かったし元気が出た!自分も頑張ろう!」そんな気持ちを持って帰ってもらえたら良いですよね。
もちろん演奏者が完全にお客さんの心をコントロールすることなんて現実的に不可能ですが、少しでも奏者の独りよがりでなく会場全体で一緒に楽しめる工夫を考えていきたいものです。
演奏後の「良かった」は社交辞令でしょうか
コンサート後にお客さんから「良かったよ」「楽しかったよ」という声をいただいたことはあるでしょうか。
この記事を読まれてる方なら「一度もない!」ということはきっとないでしょう。
ではその言葉を受け取った時、どういう意味だと感じましたか?
「よくわからないからとりあえず褒めてみたのかな」
「下手くそと思ったけど気を使われたのかも」
「社交辞令の挨拶でしょ」
せっかくの感想をそんな風に受け止めてはいないでしょうか。

お客さんとして聴きに来てくれて感想までくれるということは、少なくとも好意的に聴いてくれたはず。
「良かった」の中からどうにかこうにか否定的なものを嗅ぎ取ろうと心のなかでほじくり返すのは、あまりおすすめの反応とは言えません。
それでは自分もつまらない上に、せっかく「良かった」と言ってくれる相手に対しても失礼でしょう。
試しに一度、「いただいた感想の『良かった』はそのままの意味で良い演奏だったのだ」と受け止めてみたらどうでしょうか。
そのときにどんな気持ちになるでしょうか?
心が柔らかく温かくなりませんか?
呼吸が軽やかになりませんか?
その柔らかさや温かみは、次にまた演奏をするための心の栄養になるのです。
自分が行ったことに対して喜んでくれた人がいるというのは励みになりますもんね。
その栄養を丸めてゴミ箱に投げ捨てるのが「良かった」の裏を読もうとすることです。
どうせなら感謝と共に受け取れば良いのに、もったいないですね。
言われた通りに受け取ってみる、心掛ける価値はありますよ!



