無料メール講座
〜スキマ時間で確実に上達する〜
【管楽器プレーヤーのための練習テクニック】
ご登録で3つの自習教材をプレゼント中です。ご自由にダウンロードしてご活用ください。
楽典教材

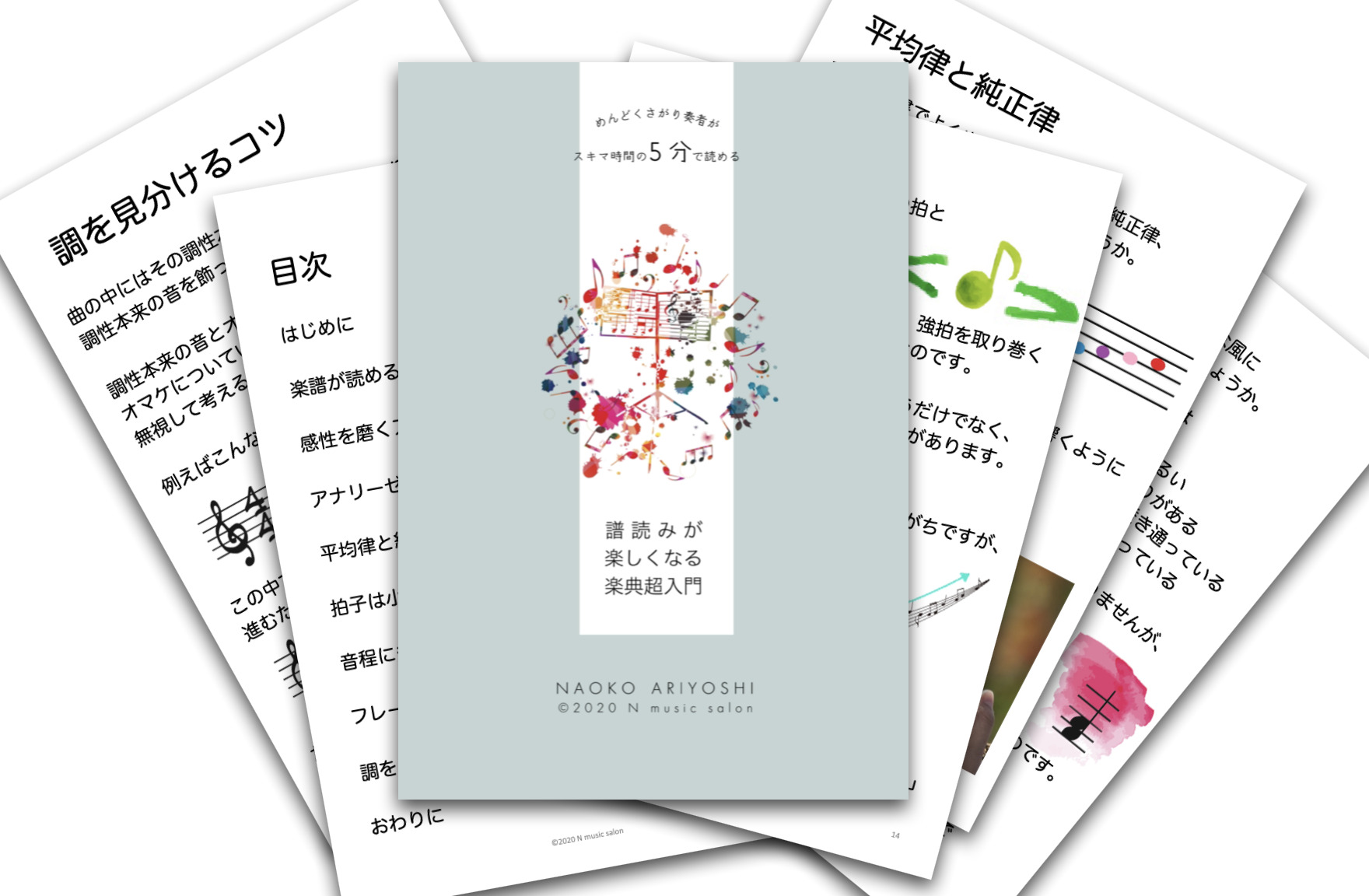
ソルフェージュ教材

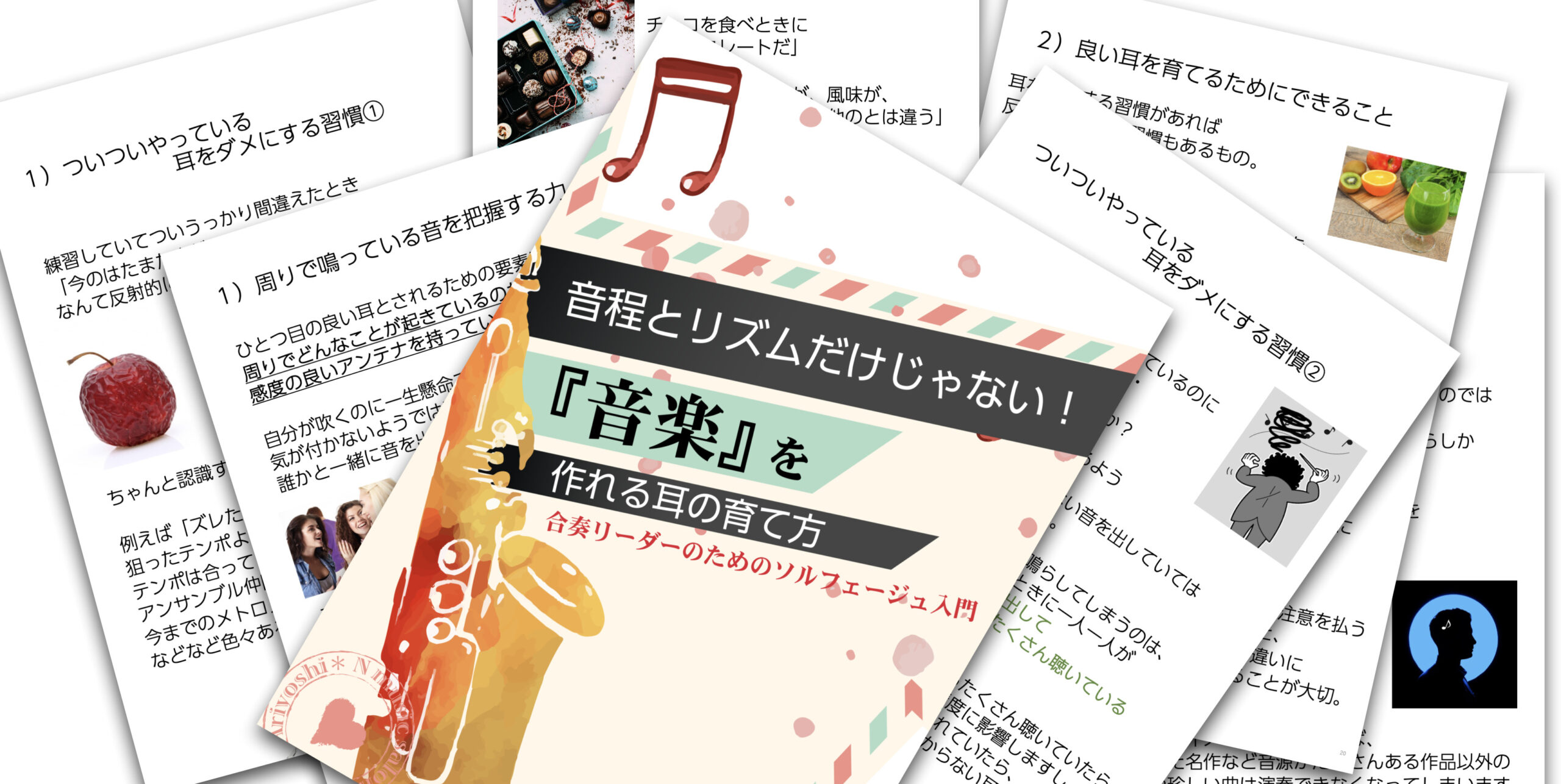
アレクサンダーテクニーク教材

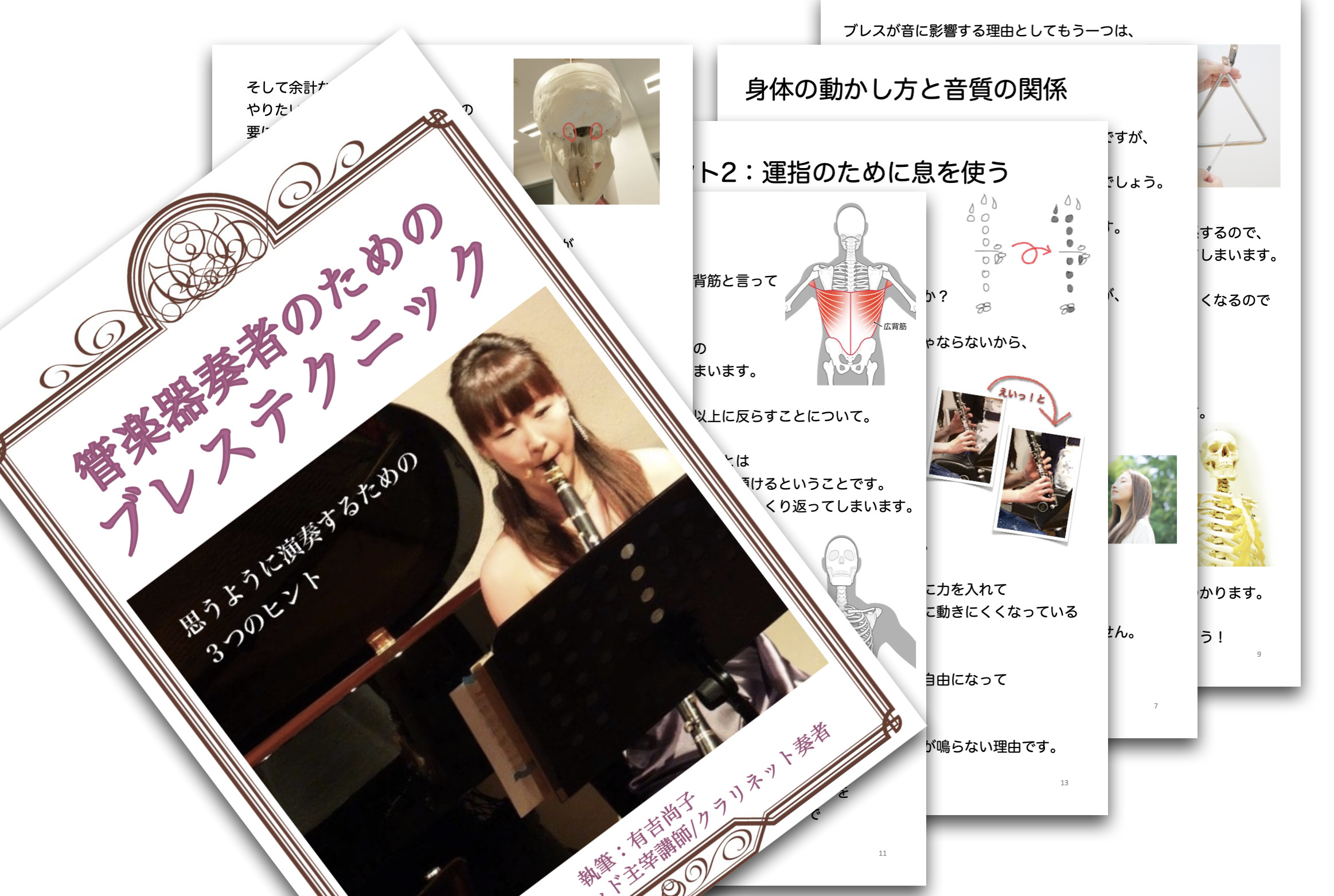
▼全部まとめてメールで受け取る▼
※ezweb・docomo・vodafone・softbank.ne.jp・icloud.com・hotmailからのご登録の場合、文字化けやメールの配信エラーが大変多くなっております。恐れ入りますが、それ以外のアドレスからのご登録をお願いいたします。
(ご記載いただいた個人情報は適切に管理し、メール配信のための情報として利用させていただきます。ご本人の同意なしにその他の目的での利用・提供はいたしません。 )

楽典教材を先に読了された方の声

*お名前、肩書、年代等は当時のものです。
クリエイティブなアプローチができるような感じがしてとてもわくわくしました!

お名前:加藤有希さん
楽器:トランペット/指揮者
年代:30代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
冊子の中に「譜読みをするというのは並んだドレミの行間からどれだけ作曲者の意図を汲み取れるか」という問いかけがありました。
「譜読みをする」行為の中で一般的に思い浮かべるのは「合奏までに頑張って音を並べられるようにならないと!」といったような縛りがあるような印象があります。
それを「どれだけ作曲者の意図を汲み取れるか」というアプローチにすることで一気に視界が開けたような、もっとクリエイティブなアプローチができるような感じがしてとてもわくわくしました!
◆どんな人におすすめですか?◆
・楽器をやっているけれど、歌い方がわからない
・楽譜は読めているつもりだけどもう少し楽譜の読み方を深めていきたい
・アナリーゼを身につけて今よりも自由に演奏したい
こんなことを思い描いている人にオススメです!
苦手意識があるという人にわかりやすい

お名前:山田喜也さん
ご職業:音楽家、吹奏楽指導者アカデミー主宰
楽器:トランペット
年代:30代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
音楽の理論や楽典は難しいんじゃないか、めんどくさいんじゃないか、と思う人は多いと思います。
ちょっと苦手意識があるという人にはわかりやすく、優しい言葉で書かれているので「なるほど!」と「そう考えるとイメージし易いな!」と思えました!
自分が感覚が多い人間なので、楽譜の読み方など教える時にも例えのお話を参考にさせていただこうと思いました。
決して堅苦しい小冊子ではなく、読みやすかったのですぐに読み終わってしまいました!
「理論」という言葉で引いてしまうのではなく、それは音楽の表現や知識を深めてもっと楽しめるようになるものなんだと思えてきます!
◆どんな人におすすめですか?◆
理論、楽典について、音符や楽譜の読み方に苦手意識がある人や、自身が教える立場の方にとても参考になると思います!
私もメルマガを読ませていただいてますが、毎回勉強させていただいてます!
もっと音楽を、楽器演奏を楽しんでいきたいという方には特にオススメします!
音楽をする上でのルールブックです

お名前:沼田司さん
ご職業:演奏家、日本トロンボーン協会 常任理事
楽器:バストロンボーン、コントラバストロンボーン
年代:50代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
音大入学の時点に、必要不可欠な楽典入門をとても分かりやすく書いている内容です。
◆どんな人におすすめですか?◆
楽典を食わず嫌いになっていて、楽器を演奏している大人の方々。
私の経験では、一般団体のレッスンに行った時、楽典の話を分かりやすく説明すると、「とても勉強になった」と言われました。
しかし楽典は難しいものではありません。
楽典は音大の入試課題です。その平均点は何と90点以上!!この90点は入試の平均点では驚異的な数字です。
言うなれば受験生(高校3年生が主)で、も簡単に点数が取れる=誰もが理解できる。
難しいことではない内容なのです。
言い換えると音楽をする上でのルールブックなのです。
例えば野球で先行後攻があり、打ったら1塁に走る。
こんな簡単なことなのです。
楽典では作曲者が書いた音楽を演奏するためのルールブックなのです。
実はこのルールを知りそれを実行するだけで音楽的表現は数ランク上がるのです。
楽典苦手と考えずに、基本的なルールブックとして知っているとお得です。
アナリーゼ=楽曲分析
と考えると面倒くさそうですよね。
日本語(すべての言語)には行間を読むと言われますが、これは感覚的なことが多いかと思います。
アナリーゼは感覚的なこともありますが、実は楽典のルールの中から理論的に導き出されるのです。
前述しましたが、楽典は音大受験で平均点90点くらいの以外にも簡単なものです。
この楽典を知れば、ややこしいと思えるアナリーゼもスルッと脳に入ってきます。
読譜が苦手だと感じでいる人、今の演奏を更に良くしたいと思う人に

お名前:手塚由美さん
ご職業:ホルン奏者・アレクサンダーテクニーク教師
楽器:ホルン
年代:50代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
読譜のセンスはスキル!努力次第では誰でも、いつからでも身につけることが出来るということです。
子どもの頃から楽器を演奏していると、自己流でもある程度の演奏は出来ると思いますが、音楽が少し複雑になると、演奏が上手な方でも急にそれについて考えるのをやめてしまうような傾向があると感じています。
それはとてももったいない!
イキイキとした音楽を演奏するために、楽典やソルフェージュをまなんで、いつでも臨機応変に反応できる力をつけたいものですね。
◆どんな人におすすめですか?◆
読譜が苦手だと感じでいる人、今の演奏を更に良くしたいと思う人。
まさにその通り!とうなずけました。

お名前:まいぷさん
ご職業:フルート講師
楽器:フルート
年代:30代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
「ドレミの並びを見てその行間からストーリーや作者の意図を読み取るのが譜読み、そのやり方を理論としてまとめたものがアナリーゼと呼ばれる楽譜を分析する方法」という文章が、まさにその通り!とうなずけました。
楽譜を表面的に読んで演奏できたような気になっている人や、アナリーゼは難しいからちょっと…と思っている人は多いと思いますが、それに抵抗がある人でも、やってみようかなと思えるような書き方がされていて、とても良いと思いました。
◆どんな人におすすめですか?◆
機械のような演奏だと言われたりしたことがあって、それに悩んでいる人
音楽理論難しそうだからやらない、自分は感覚だけで演奏すればいい と思っていた人
「アナリーゼ」という言葉を聞くだけで毛嫌いしていた人
にオススメだと思います。
自然に学べてあっという間に読める

お名前:牧野千城さん
ご職業:声楽・ピアノ・カラダの使い方コーチ
楽器:歌・ピアノ
年代:50代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
この冊子は、譜読みをする上でなぜ楽典が必要なのか?、それを知るとどのように役に立つのか?を、初心者の方にもわかるように例えをあげて説明されています。
堅苦しいものはなく自然に学べてあっという間に読めてしまい、続きが楽しみになりますよ♪
◆どんな人におすすめですか?◆
楽典や譜読みという言葉を聞いただけで「難しそう〜」「勉強するのは苦手〜」という方
楽器は演奏できるけど、どうも音楽的にならないと感じている方
楽典を知らないのは人生の無駄づかい!

お名前:いちろーたさん
ご職業:バイオリン講師
楽器:バイオリン
年代:40代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
楽典を知らないのは人生の無駄づかい!
そんな思いがあちこちから溢れてくるような、尚子さんの講座での熱い語りがそのまま冊子になってます!
読んでいくと、「この一文は○○○○のことだな」「講座のなかで言われてたこと、ここでも強調されているな」とうなづきながら復習にもなりました。
◆どんな人におすすめですか?◆
楽典をやってみようと思って挫折した人
初見の苦手意識を克服したい人
音を並べて終わってしまう練習から表現を磨くための練習に脱皮したい人
やりたい音楽をうまく言葉で説明できるようになりたい人
この冊子を読んで、音楽のある人生の素晴らしさを満喫する人が増えることを願っています!
どんなふうに役に立つのか、がよく分かります!

お名前:渋谷啓子さん
ご職業:クラリネット講師・奏者
楽器:クラリネット
年代:40代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
ちょいちょい出てくる例え話もとても分かりやすくて、楽典の大切さが実感できます。
「楽典」もしくは「理論」とまとめて考えてしまいがちですが、具体的にどんなものがあって、どんなふうにつながっているのか、どんなふうに役に立つのか、がよく分かります!
◆どんな人におすすめですか?◆
もっとよいパートリーダーになりたい、もっとよい指揮者になりたい、など意欲のある人。
楽譜は「見る」ものだと思っていて「読む」と言われてもピンと来ない人
「楽器が吹ければいいもん。」と思ってる方に

お名前:間瀬早綾香さん
ご職業:マリンバ奏者
楽器:マリンバ
年代:40代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
一つ一つの「音楽の勉強」がなぜやらなくてはいけないのか?というのがとても丁寧に書かれています。
◆どんな人におすすめですか?◆
「楽器が吹ければいいもん。」と思ってる方。
「楽典は難しそう」と思ってる方。
「音楽の勉強をするのはめんどくさい」と思ってる方。
コロナで疲れてる方。
入門の入門とでもいうようなガイドになっている

お名前:梅本周平さん(Wind Band Press/ONSA)
ご職業:自営業
楽器:クラリネット
年代:40代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
専門用語も出てきますが、それをなるべくわかりやすい言葉に置き換えて入門の入門とでもいうようなガイドになっている点でしょうか。
◆どんな人におすすめですか?◆
「そもそも楽典ってなんだろう?」
「音楽理論って難しそうだし無理」
そんな風に考えている人でも、
「でも理解できるようになれば音楽がもっと楽しくなるな」
ということはわかるようになっている入門冊子ではないでしょうか。
まずは心の壁を取り払いたいな、という方にオススメです。(3分程度なので)
楽譜から見えてくる景色が変わる、ということに共感しました

お名前:いろんなセンセイさん
ご職業:演奏家、大学非常勤
楽器:オーボエ
年代:40代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
楽譜から見えてくる景色が変わる、ということに共感しました。
楽譜の情報をどこまで読み取れるかは、その人の表現に大きく影響してくることだから。理論を勉強する楽しさも伝わってきました。
◆どんな人におすすめですか?◆
もっと曲に合った表現したい人や歌い方がわからない人、楽譜からの情報をもっと知りたい人など
アマチュアでも楽典やアナリーゼを学ぶ必要があると切に思いました
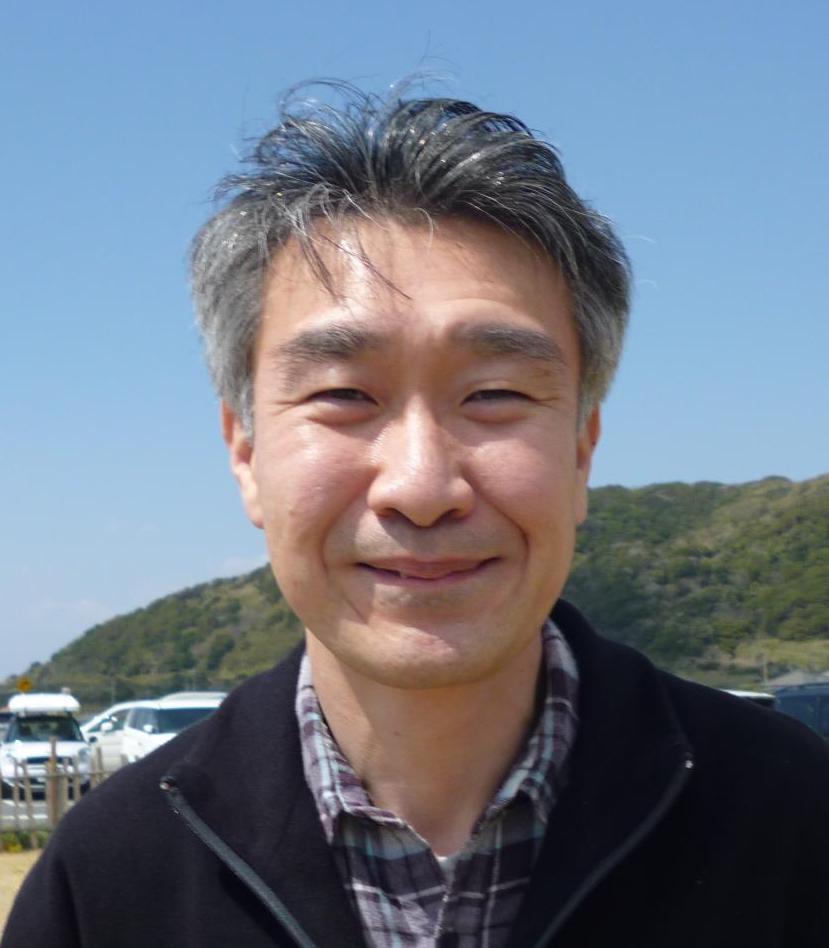
お名前:コージさん
ご職業:公務員
楽器:クラリネット
年代:50代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
アマチュアでも音楽をやるからには、楽典やアナリーゼを学ぶ必要があると切に思いました。
◆どんな人におすすめですか?◆
楽典やアナリーゼをきちんと学んだことがない人
もっと学んでみたいと思わされるような内容でした

お名前:meraさん
ご職業:演奏家、講師
楽器:二胡
年代:50代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
楽典って難しそうだと思っておりましたが、書物を読んだだけでは理解しにくいような事を、具体的なイメージを挙げながら説明されていて、もっと学んでみたいと思わされるような内容でした。
音程にも一つ一つイメージがあって、「明るい」とか「透き通った」とか「陰りがある」等々…、と説明されている所で、挿絵にパレットや水彩を使ったものが使われていたのが印象的で、作曲をする時には、絵を描く時に一つ一つの色合いを選ぶように、音を選ぶのかなぁ、などとイメージを膨らませながら読ませていただきました。
使われている挿絵は、全てイメージに合っていて効果的だと思いました。
◆どんな人におすすめですか?◆
音楽をやっているけれども、専門的に楽典を学んだ事のない人。
趣味で楽器を弾いている人でも、これからもっと表現を磨きたいと思っている人。
曲を作ってみたいと思っている人。
「楽譜を読み解く力」を持っていることは“お得”だと思います
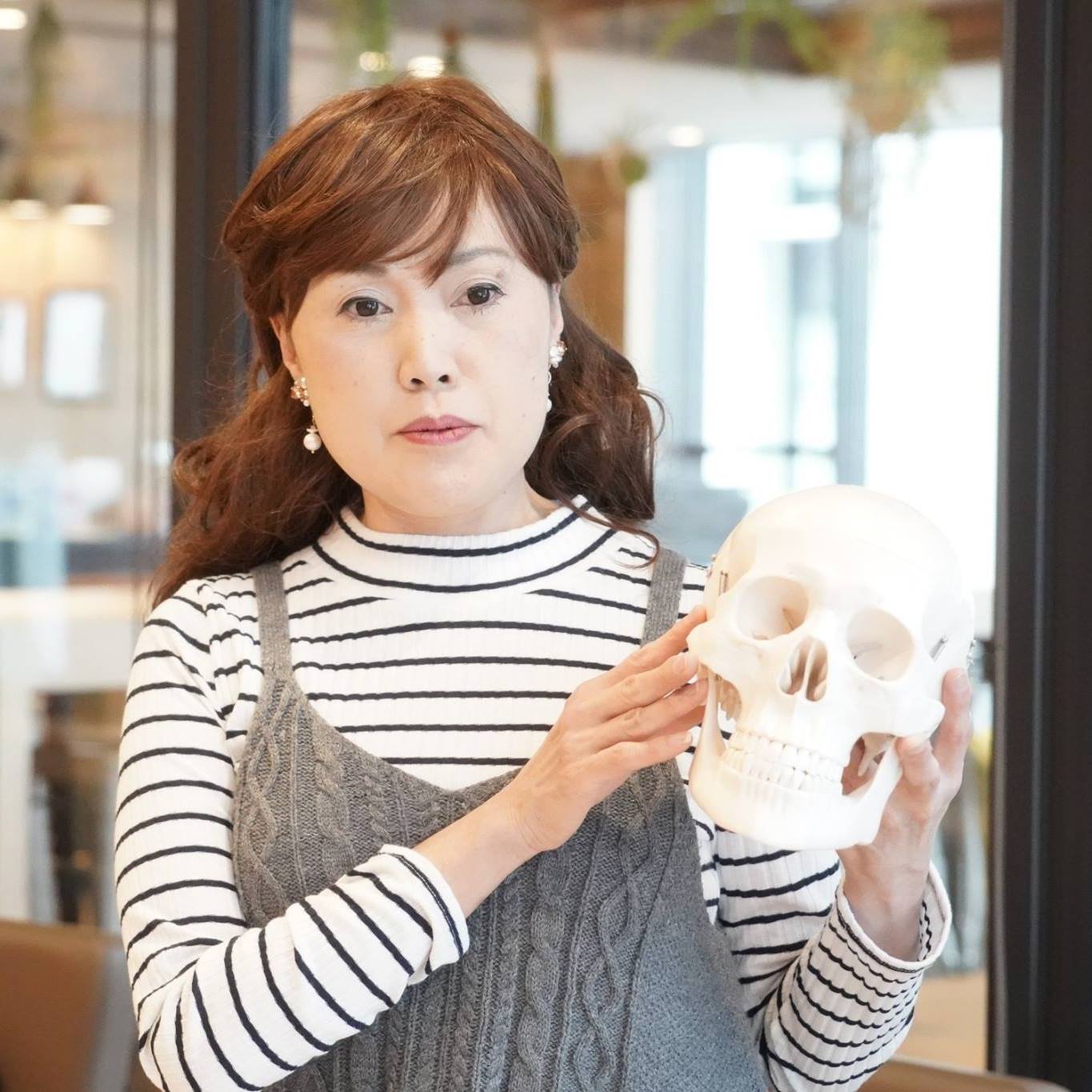
お名前:小林利絵子さん
ご職業:アレクサンダーテクニーク教師
楽器:声楽
年代:50代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
・すっかり忘れておりましたが、こんなこと勉強したな~と思い出させていただきました。
・“アナリーゼ”と言う言葉を初めて知り、興味を持ちました。
・「楽譜を読み解く力」を持っていることは“お得”だと思います。
・とても分かりやすいので、楽典に興味を持ちました。
・尚子先生の伝えたいことが、しっかり詰まっていると思います。
・ことばの選び方に優しさを感じます。
・イラストや写真がかわいいです。
◆どんな人におすすめですか?◆
・楽器を習っている小学生~中学生。
・大人になってから楽器を習い始めた向上心のある中高年(特に男性)
楽譜を読み直し、早く演奏したくなりました。

お名前:mumuさん
ご職業:作曲、演奏
楽器: 鍵盤等
年代: 40代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
アナリーゼについてのこと。
「拍子は1小節が1まとまりではなく強拍を取り巻く盛り上がりから収束までが1セットなのですね。」という言葉。
尚子さんの優しいお顔と声が浮かぶようでした。
楽譜を読み直し、早く演奏したくなりました。
◆どんな人におすすめですか?◆
初心者はもちろんのこと、楽典を習ったことがある人にも。
思いがけない発見がたくさんありそうですよ!
音楽を始めたばかり、またレッスンに通っている人に

お名前:IMさん
ご職業:音楽家
楽器:ピアノ、指揮
年代:30代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
何を学んだら、楽譜をもっと日本語のように読めるのか、好きになれるのかが具体的でわかりやすいです。
◆どんな人におすすめですか?◆
音楽を始めたばかり、またレッスンに通っている人
または音楽を合奏・合唱で楽しんでいる皆さん
指揮者や仲間の言わんとしていることがピンとこないことがある人に

お名前:黒田悦子さん
ご職業:ピアノ講師
楽器:ピアノ・ヴィオラ
年代:40代
◆どんなことが印象に残りましたか?◆
とてもわかりやすいです。
実際の楽譜と照らし合わせて演奏したらより理解できて楽しいですね。それはレッスンで、ですね!
楽譜と向かい合う楽しさを知ってもらいたいです!
◆どんな人におすすめですか?◆
楽器経験はそれなりにあるけど、指揮者や仲間の言わんとしていることがピンとこないことがある人とか、なんとなくやっていてたぶん間違っていないけど…なんで?と思うことがある人とか。
ソルフェージュ教材を先に読了された方の声

*お名前、年代、肩書等は当時のものです。
『聴く』ということの意味をこんなにうまく解説している文章を初めて読みました。

フルート奏者/フルート講師
アレクサンダー・テクニーク教師
嶋村 順子さん
音楽の演奏には聴く力は本当に大切です。
聴くということの意味をこんなにうまく解説している文章を初めて読みました。
「演奏」の中にはたくさんの要素が含まれると思います。
楽譜に書かれているだけでもとてもたくさんの情報がありますし、それらを汲み取る力は演奏には必要です。
自分なりの表現、とよく言われますが、曲の持っているスタイルや性格にマッチしていない演奏、つまり素材を無視した料理法は残念な作品になってしまうでしょう。
一緒に演奏する仲間とのバランスや、聴いているお客様の存在、そんなことも「演奏」の要素には含まれます。
専門的な教育を受けた人たちは、長い時間をかけて適切な導きのもとに知らないうちに身につけていることが多いのですが、それはとても恵まれていて幸せなことなのだな、とつくづく思います。
大人になって演奏をしたいという夢を持った人たちにとって、「演奏って本当は何が大事なの?」と言う壁にぶつかる頃があると思います。
その一つがまさに、演奏する人が備えているべきこのソルフェージュ能力なのです。
この言葉で説明することの難しい大切な「基礎力」について、この冊子はとってもわかりやすく、そして大人が腑に落ちる解説となっています。
熱意もあって努力もしているのに「演奏」がなぜかしっくりこないのは、必要な「基礎力」が不足していたからかもしれません。
この冊子を読んだ大人の楽器愛好家の方で「これが足りないのかも」と思った方は、もうどんどん学ぶ方がいいですね!
きっと、もっともっと演奏が自分のものになってくるはずです。
合奏でよく指揮者に注意される方にオススメ

ONSA代表 Wind Band Press編集長
梅本 周平さん
楽器:クラリネット
演奏に役に立つことはありましたか?
これを読んでいる方が今どのような演奏レベルにあるかに関わらず、「おろそかになりがちな基本」または「基本ということが知られていない基本」について簡潔にまとめられています。
特に「楽譜から音楽をイメージする」の項は、楽典などで勉強をしていないアマチュア奏者にとっては「勉強は避けて通りたいけどこれを出来るようになればいいのにな」と思うことについて、「やってみましょう」と背中を押してくれるような項なので勉強に手を付けるきっかけになるかもしれません。
演奏に役立つかどうかは読者のやる気に委ねられる冊子ではありますが、実践すればきっと演奏活動の一助になることでしょう。
どんな人におすすめですか?
主に社会人のアマチュア奏者向けの内容かと思います。
学生時代の練習習慣を特に理由なくそのまま続けている方や、書籍やネットで見た記事や意見を参考にしてみたりして何かを変えようとしているのだけれどなかなか上手くいかない方、練習する時間があまり取れない方、そして合奏でよく指揮者に注意される方。
もう少し具体例を挙げると、
- 「何かが上手くいっていない気がするけど何から手を付けて良いのかわからない」
- 「練習する楽しさが以前に比べてあまり感じられなくなってきた、正直つまらない」
- 「楽団の人は好きだけど合奏は苦行なので練習に参加するのが面倒だ」
- 「自分の音を聴かれるのが怖いのでなんとなくそれとなく存在感を消している」
- 「ただ音を出すだけではなくて音楽をしたい、表現のための活動を楽しみたい」
そんな様々な不満や悩みをお持ちの方にオススメですね。
リーダーのみならず全ての作音楽器の方にしっかり読んで頂いて感じて欲しいです。

クラリネット奏者
藤井一男先生
演奏に役に立つことはありましたか?
作音楽器である弦・管楽器は一応音を出すポジションや指の位置は決まっていますが、そこから先に音作る作業があります。
微妙な音程、表情など。そのことに気付かせてくれるポイントが満載です。
どんな人におすすめですか?
リーダーのみならず全ての作音楽器の方にしっかり読んで頂いて感じて欲しいです。
当たり前にやりがちなちょっとした習慣についてハッと気づかせてくれます。

アレクサンダーテクニーク教師
沖縄県立芸術大学非常勤講師
ホルン奏者
バジル・クリッツァーさん
演奏に役に立つことはありましたか?
自分が音痴かも、とか、合わせるのが下手というように内心不安な方にとって、「耳が良い」「音程感がよい」「アンサンブル能力が高い」というのはどういうことなのかを正面からわかりやすく説明してくれる冊子です!
音程やアンサンブルの力を「損なう」意外な、多くのひとが当たり前にやりがちなちょっとした習慣についてもハッと気づかせてくれます。
どんな人におすすめですか?
音程、アンサンブルなどがうまく合わせられずに悩んでいるひと。
自分が音痴なのじゃないかと気にしているひと。
ソルフェージュというものが何なのか実はあまり知らないのだけど、知らないのが恥ずかしくてひとに聞けずにいたひと。
音楽の基礎や、経験が足りないんじゃないかと気になっているひと。
無意識に「心のシャッター」に手がかかってしまう方へ

サクソフォン奏者
アレクサンダー・テクニーク教師
渡邊 愛子さん
演奏に親しむ方々なら、どこかで必ず触れたことがあるであろう「耳がいい」「耳が悪い」という言葉。 この言葉に、切なさを感じる方も多いと思います。
「あぁ、もっと耳が良かったら…」 あるいは、この言葉を聞くと無意識に「心のシャッター」に手がかかってしまう方もいるのではないでしょうか。
「ごめんなさい、わたし、耳が悪いから…」 そもそも、この音楽を聞く上においての「耳の良さ」というものは一体何を指すのでしょう。
この冊子では、そのことについて優しく、そして丁寧に解説されています。
音を聞く力は、幾つになっても開発し、伸ばすことができます。
それは明確な数字にすることはできるものではないので、はっきりと実感することは難しいかもしれませんが、きっとそれによってあなたの「音楽の世界」はもっと楽しく、大きく、深く、また新たなものになってゆくでしょう。
『もっと聞けるようになりたい』 『もっと音楽を楽しみたい』 そんな願いを持つ大人の皆さま。
「心のシャッター」から一度手を離し、子供のような好奇心と音楽を愛する心を持って、ぜひこの冊子をお読みください。音楽の扉はいつも開かれています。
この冊子は、そこへ向かうあなたの小さな一歩を力強くサポートしてくれます。
ひたすら指さらいを練習していましたが、本当に必要だったのは音楽の理解の仕方だったのですね。

bodytune鍼灸マッサージ院 院長
楠 洋介さん
楽器:コントラバス
演奏に役に立つことはありましたか?
アマチュアでコントラバスを弾くのですが、所属オケで展覧会の絵をやっていて、臨時記号の速い運指がいつも頭の中でこんがらがってうまくできませんでした。
それが有吉さんのソルフェージュ講座を1回受けただけで音階の途中から始まっていることが見えてすんなりできるようになりました。
運指は変えてなくて、理解の仕方を変えたことがブレイクスルーでした。
アマチュアでずっとやっていると楽譜の音をひろうことはできますが、その意味を含めて学ぶ機会がありません。
単語をたくさん覚えた方が勝てる受験英語と同じで、長大な時間をかけるわりには一向に話せるようになりません。
上のケース、僕は指の問題だと思ってひたすら指さらいを練習していましたが、本当に必要だったのは音楽の理解の仕方だったのですね。
この一件で、いやソルフェージュ本当に役に立つし必要だと思いました。
どんな人におすすめですか?
アマオケや一般バンドで何年もやっているのに、演奏会のたびに新しい曲目を仕上げるのにとても時間がかかる方におすすめです。
これは僕自身そうですが、1つのプログラムに取り組む中で学んでいることがたくさんあるはずなのに、曲目が変わると全然その経験が生かされず、ゼロから再スタートする感じが何年もありました。
アルファベットや単語を十分学んだら、次は文法や読み方、話し方を学ぶ必要があるのですね。言語の場合は言葉自体に意味があるので量をこなせば自然と分かってくるものもありますが、音楽の場合は音そのものには意味がありません。だから専門家に教えてもらうのが効率的だし、また必要です。
日々の努力で音感はアップするのです。

トロンボーン奏者
浜松学芸高等学校音楽科非常勤講師
BodyThinking、ThinkingBodyコーチ(BodyChance認定)
片山 直樹さん
有吉尚子さんのソルフェージュ講座は、以前から私自身が受けたいと思っていました。
ソルフェージュというものの概念が私の中では「音を頭の中で鳴らす」程度の単純なものであり、でもそれだけじゃないと思いつつも色々なこととうまく結び付かないでいました。
有吉さんは、そんな私のソルフェージュ概念にザクザクとメスを入れてくる講座をしていらっしゃいます。受けたくなるのも当然です。
今回ソルフェージュに関する冊子を作られたということで、早速読ませていただきました。
音を聴く能力というのは決して生まれ持った才能ではなく、日々のトレーニングでアップすると言うようなことが書かれています。
これは私も全く同感です。日々の努力で音感はアップするのです。
さらにこの冊子の内容で素晴らしいところは、その日々の努力の仕方が書いてあります。そしてその努力の方向が、方法ではなく意識に向いているところ。
ほんのちょっと意識の向け方を変えることで、短時間で効率的に能力をアップさせることができるという過程の説明も、さすがアレクサンダーテクニーク教師と思えるアプローチをしています。
なにより、内容がわかりやすい!これ重要☝️
いいこと書いてあっても、文が難しいと読む気なくなってしまいますもんね。
演奏にとってソルフェージュは必要と漠然と思っていた方や音を聴く意味を深く考え理解したいと思っていた方はもちろん、音をもっと聴けるようになりたい、演奏力を上げたいと実践で使えるスキルを身に付けたい方、また指導に手詰まりを感じたりいいアドバイスの仕方を知りたいと思っている方には、とても役に立てることのできる内容と思います。
オススメです。
大人プレーヤーだけでなく音楽を専門にしている方にも

テューバ奏者
吹奏楽指導者
アレクサンダー・テクニーク教師
石川 佳秀さん
演奏に役に立つことはありましたか?
自分が経験して得たもの、体験を通して身につけて来たものを言葉や文章にしようとした時、上手い言い回しが見つからなかったり、どう表現したら良いか分からない事がありますが、この冊子にはそういう「表現しにくい」ことについても分かりやすい言葉で、読みやすく書かれていると感じました。
「耳の良さ」という言葉について、感覚的にやっていること大切にしていることはあっても、正直、私の中ではそれを言葉にしようとした時に少し漠然としたところがありました。
しかし、この冊子のようにどんな要素で成り立っているのか、どんな力がそれを指しているのか順序立てて書いてあると、大人プレーヤーだけでなく音楽を専門にしている方も「なるほど、確かにそうだ!」と納得出来るのではないでしょうか。
どんな人におすすめですか?
自分の演奏のレベルアップを考えているけど、具体的に何をしたら良いか分からない人や、どんな力を身に付けることが必要なのか分からない人には最適だと思う。
内容としては大人プレーヤーに向けて書かれているのだと思いますが、良い演奏をしたいと頑張っている、これからステップアップしたいと考えている、吹奏楽部の生徒さん達にも役立つように感じます。
というか、僕はこれを読んで先ず自分の生徒さん達に読んで欲しい!と思いました笑
尚子さんのレッスンを受けているような感覚で読める素敵な冊子だと思います。
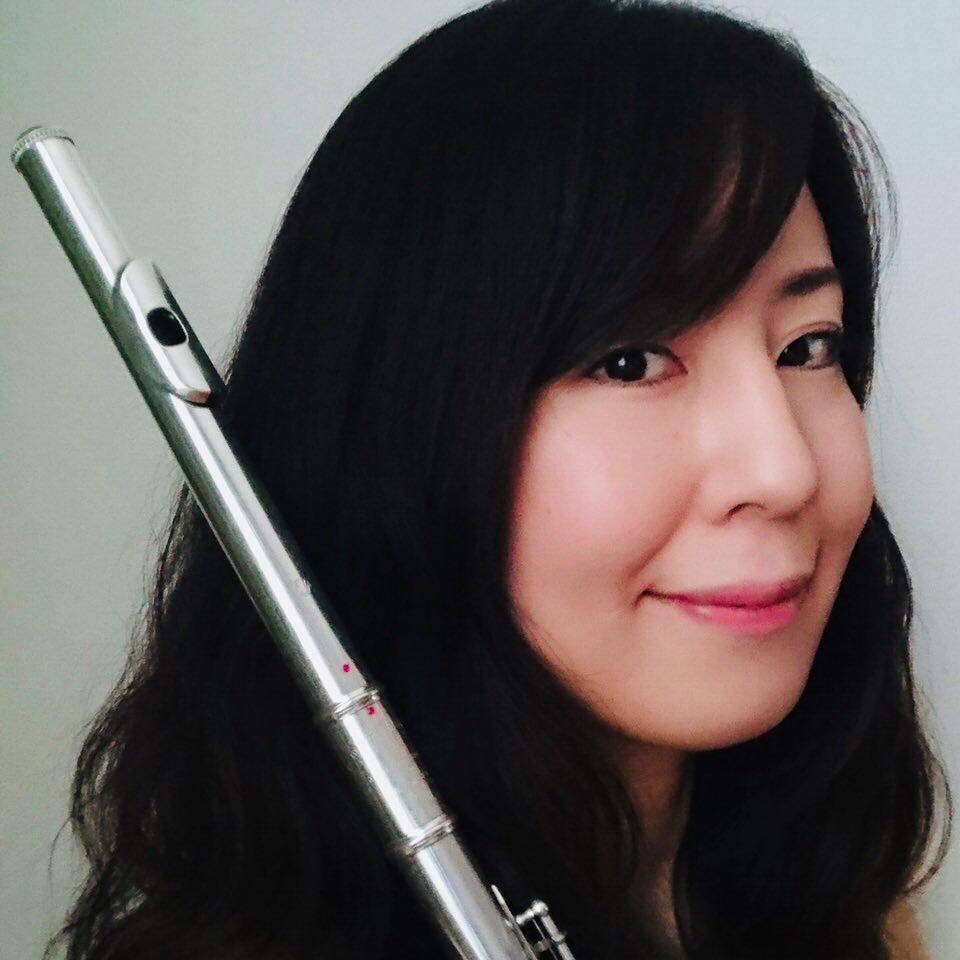
フルート吹き・講師
中林暁奈さん
演奏に役に立つことはありましたか?
ぎっしり盛り沢山です!!
演奏はもちろんのこと、自分自身を見つめ直すきっかけにもなるのではないでしょうか。
日常生活の中での意識や経験が、音楽の重要な材料になることを改めて理解できると思います。
どう演奏したいのか、楽器を持たない状態で冷静に頭の中を整理し、トレーニングを重ねていくことで、自分の音楽を確立でき、自信がつき、より楽しさを感じることに繋がっていく・・・そうなれるまでに具体的にどのようにすればよいのか、沢山のヒントが散りばめられています。
どんな人におすすめですか?
どんな人にもおすすめしたいです!
尚子さんのレッスンを受けているような感覚で読める素敵な冊子だと思います。
とても分かりやすい言葉と、イメージしやすい表現で書かれているので、本を読むことが苦手な私でも最後まで興味を持って楽しく読むことが出来ました。
きっと、ポジティブ菌が増え、やる気が湧いてきますよ♬
自分のやりたい音楽の方向性を明確に

アレクサンダー・テクニーク教師
オーボエ奏者
村瀬 正巳さん
アレクサンダー・テクニーク教師仲間の有吉さんが、ソルフェージュを学ぶための小冊子を発行するとのこと。
興味があってサンプル版を拝読しました。
「ソルフェージュ」という言葉に、管楽器奏者はどれくらい興味を持てるものでしょうか。「歌を歌うわけじゃないし、関係ないよね。」とか、「ド」の指を押せば「ド」の音が出るし、とか思ってる人が多いかもしれませんね。
有吉さんの今回の小冊子には、楽器を演奏するために、そして仲間と幸福感を持って音楽を奏でるために、ソルフェージュのことを考えてみてはいかが、という提案が愛情を持って書かれています。
音楽という媒体は、人々にとって生きていくのになくてはならない糧なのだと思っています。
そうなるために、単に耳で聴いて合わせましょう、ということにとどまらず、自分のやりたい音楽の方向性を明確に持ち、楽譜から作曲者の思いをどのようにして詳らかにしていくか、このことを大事にすることの必要性を優しく皆さんに提案しています。
有吉さんは、人間にも音楽にもとても深い愛情をお持ちなのでしょう。どちらとのお付き合いも疎かにして欲しくない、という気持ちがあふれています。
皆さんも同じように愛情を持ってくださるだけで、音楽の場が今の在り様とは随分と様変わりすることを期待します。
ぜひお読みください。
特にソルフェージュ能力確認の簡単なテストがオススメです。

楽譜浄書家・吹奏楽指導者
新垣 賢司さん
楽器:管打楽器全般
演奏に役に立つことはありましたか?
より良い演奏・アンサンブルをするために必要な知識や考え方がわかりやすく説明されています。
ソルフェージュとは何か、その能力を伸ばすにはどうすれば良いのか、そのヒントがたくさん詰まっています。
特にソルフェージュ能力を確認するための簡単なテストはオススメです。
どんな人におすすめですか?
独学で演奏活動をされてきた人、プロのレッスンを受けたことが無い人、自分の演奏に何が足りないのかを知りたい人。
自分らしく死ぬまで!?演奏活動を楽しんでいって欲しいです。

ホルン奏者
アレクサンダーテクニーク教師
手塚由美さん
生徒さんから「耳が悪い!」「もっとよく聴いて」という指導されたことがあると聞きます。専門的な音楽の勉強をしていない人に対して具体的に「聴く」ということや、「よい耳」を育てていくと、こんなに演奏に役立つことがある、などという大切なところが抜けてしまっていると思います。
耳を育てること(ソルフェージュ)って音大へ行く人だけが必要だと思っていたらもったいないなぁ〜と思っていたので演奏する全ての人にオススメしたいです。
尚子さんの冊子を読んでこんなに演奏にいいことがたくさんあるなら、少し試してみようかな〜と思う人が増えて自分らしく死ぬまで!?(笑)演奏活動を楽しんでいって欲しいです。
管楽器奏者はブレスの場所も選びやすくなります。

クラリネット奏者
佐藤 麻紀さん
演奏に役に立つことはありましたか?
素直にソルフェージュがなぜ必要なのかという事が書いてありました。
楽器を習う機会はあっても、ソルフェージュのレッスンを受ける事は主流で無いような気がしています。
音の関係性が分かってくると、例えば管楽器奏者はブレスの場所も、選びやすくなります。
細かい一つ一つを話したらキリがありませんが、演奏するに当たって、ソルフェージュは大切な作業の一つだと思います。
どんな人におすすめですか?
ソルフェージュはプロ、アマチュア関係無く音楽家、全てに共通して必要な項目だと思いますが、この本に関しては、アマチュアで楽器を演奏する人に宛てて書いているように思えました。
単なる知識を列挙したものとは次元が違うようです。

会社員
YSさん
楽器:トランペット
演奏に役に立つことはありましたか?
ソルフェージュと聞くと、音符あてのようなにおもったのですが、この冊子でを読むにつれ、印象が一変しました。
また、この冊子は、著者が実際に楽器を通し音楽を極めていこうとされた苦労と経験の過程で得られたもので、単なる知識を列挙したものとは次元が違うようです。
そして「なぜ」だめなのか、「どうしたら」いいのかもわかりやすく説明されています。
言葉の中に演奏家としての経験が込められているため、一字一句が貴重で大変参考になりました。
どんな人におすすめですか?
指導者、プレイヤーのみならず、音楽力を向上させ深く堪能したいとおもわれていらっしゃるリスナーの方にも
アレクサンダーテクニーク教材を先に読了された方の声

*お名前、年代、肩書等は当時のものです。
苦手な課題がある時に『部分ではなく体全体をどう使うか?』

ホルン&ピアノ教師
手塚由美さん
50代
呼吸が上手くいってない人はブレスについて興味があると思いますが、尚子さんのブレステクニックではブレスをする時の体の使い方でタンギングにも影響したり、フィンガリングにも影響があるということを知り試してみたくなると思います。
知識として知っていても試さないと何にも変わらない。
試さないなんて1万円落ちてるのに拾わないようなもんです。
何か苦手な課題がある時に
『部分ではなく体全体をどう使うか?』
というとところにポイントを置いて練習すると今までと違う発見がありそうですね。
管楽器奏者だけでなく演奏するすべて人にオススメです。
しかもpdfのプレゼントの他に最後まで読んだ方への秘密のプレゼントまであるなんて!!
太っ腹な尚子さんです
(尚子さんはスリムですよ)
アレクサンダーテクニーク資格取得記念、このチャンスをみなさんぜひゲットしてくださいね!
これが無料!?ブレスに関する悪い思い込みが全て解決します

管楽器上達メンタルナビゲーター
ホルン奏者
竹内ヨシタカさん
20代
管楽器を演奏する人にとって、ブレスというのはとても気になるワードの一つだと思います。
でも、実際にブレスについて学ぼうとしても、なんとなく
「お腹を使えばいい」とか、
「しっかり吸ってしっかり吐く」とか、
そんなあやふやな言葉でしか、ブレスについて教わってないのではありませんか?
この冊子は、アレクサンダーテクニーク教師である有吉さんならではの、
からだの仕組みに沿った呼吸の仕方を、丁寧に教えてくれています。
このレベルのものがタダで読めるチャンスはそうそうある事ではありません!
ブレスについてもっと深く知りたい方、あなたの1番良い奏法を発見したい方はこの機会をお見逃しなく!
普通の教則本では絶対に書いてないこと書かれています!

マルチプレーヤー
音楽プロデューサー
斉藤彰広さん
30代
まず、無料でこの情報量はすごいです。
普通の吹奏楽系の教則本などでは絶対に書いてないことが惜しげもなく書かれています。
ブレスは管楽器奏者ならば、全員がぶつかる壁だし、興味の対象だと思います。
でも、意外に感覚でコツを教えられることが多く、『他の人には合うけど、自分には合わない! 』という悲劇が起こりやすい分野だとも思います。
そのブレスについて、この冊子の中で とても客観的に、かつわかりやすくすぐ実際に活かせるように有吉先生は解説なさってくれています!
これを手に取らなかった管楽器奏者はきっと人生単位の大損をすることになると思いますのでぜひとも迷わず手にされることを強くお勧めいたします。
クラシック、吹奏楽、ジャズなどジャンルを問わず、全ての管楽器奏者におススメできる一冊です!
この冊子は3つの小さなヒントを紹介してくれています!

アレクサンダー・テクニーク実習生
外池 康剛さん
30代
テューバ奏者
有吉尚子さんの呼吸の冊子はとてもコンパクトに、分かりやすくまとまっています。
僕がなおこさんのこの冊子を一番オススメしたいのはもちろんクラリネット奏者の方ですが、僕のように金管楽器を演奏する人にもオススメの内容です。
(呼吸の質は身体全体のコントロールと深く関わっていますから、結局は管楽器にも限らず、あらゆる分野の音楽家にとって、大切なテーマなのです)
この冊子は3つの小さなヒントを紹介してくれていますが、僕のお気に入りはヒント1です。
呼吸については色々な人が色々なノウハウを提唱していますが、本当にシンプルですぐに効果が得られる考え方は「呼吸の邪魔をしないこと」に尽きます。
そのためには呼吸に関わる身体のデザインを理解しておくこと、何が呼吸にとって不必要であるかを正確に知っておくことが大切です。
なおこさんの冊子を読むと、この辺りの基本が簡単に理解できますよ(^_^)
最後まで読んだ人には得るものがたくさんある冊子ですから、ぜひお手元でじっくり読んでみてください。
音楽の好きな熱意ある人にこの冊子が届きますように♩
身体が痛くなるばかりの学生だった自分に教えてあげたい

テューバ奏者
吹奏楽指導者
アレクサンダー・テクニーク教師
石川 佳秀さん
30代
管楽器の演奏で活かせそうなことが詳しく分かりやすく書いてありました。
感覚的に『こうすると良いような気がする』と思っていることが、的確な言葉で解説をされていました。
また、言葉だけでは無く簡単な図が入っているのが良いですね。
冊子の最初の方に書いてあった、
『一人一人違った骨格構造であることを知って、自分に・その人に合うやり方を探すのが⼀番有効です』
という言葉、とっても大切なことだと感じます。
先生や友人がやっている事を真似ても上手くいかず、身体が痛くなるばかりだった学生の頃の自分に教えてあげられたらどんなに良いだろうと思い返しました。
身体に痛みを感じる人だけで無く、自分自身の技術を伸ばしたいと考えている人、また誰かに教えたい人に役立つと思います。
最短距離で問題を解決するヒントが満載です!

鍼灸師
コントラバス
楠 洋介さん
40代
bodytune 鍼灸マッサージ院
鍼灸師の楠洋介です。
FBの知り合いがかぶってるせいか、なんか最近、有吉さんのブレステクニックばっかり出るようになってしまいました(笑)
正直、『管楽器やらないからどうだかな〜』
と思いながら、半ばSNSのじゅうたん爆撃に根負けしてポチッとしたわけですが、、、
いや、けっこうどころかすごく勉強になります。
うちの治療院にも管楽器のお客さまいらっしゃいますが、首、肩、腕あたり、
『何でそんなふうに痛めたりコリがひどくなったりするのかな?』
と常々思ってたわけなんです。
で、そんな疑問のほとんどについて何が原因か明確に書いてあります。
治療家として、当然そうした疑問を解くべく動作分析したり専門書で調べたりするのですが、何の意味があってその動きをするのかは演奏家でないとやはり分かりません。
同じスクールでアレクサンダー・テクニークを学んできた共通のバックグラウンドがあるからより納得する部分もありますが、むしろ、演奏家が自分で考えて
乗り越えたプロセスを経て結晶化したということが大きいと思います。
誰が読んでも分かりやすく、最短距離で問題を解決するヒントが満載です。
今度、管楽器のお客さまがいらしたら、これをアンチョコにして問診に役立てます!
有吉さん、ありがとうございました!
楽しく学べるステキなものです!

トロンボーン奏者・指導者
片山直樹さん 40代
呼吸と身体の関係が、アレクサンダーテクニーク面からの理論と、有吉さんのセンスが相まって、とても分かりやすく書かれていると思います。
タンギングや金管楽器奏者で必要な唇の振動に対し、
漠然と「呼吸が大切」と書かれているものは多いですが、
これには
「なぜ大切か」
「何が大切なのか」
「身体とどう関わるのか」
など、具体例を挙げて書かれています。
挿入画もかわいいものが多く、楽しく学べるステキなものに出来上がっていると思います。
ひとつひとつ教えてくれる一冊です!

トロンボーン吹き、
作編曲家、吹奏楽指導者
福見吉朗さん
身体の仕組みにかなった自然な使い方をすること。
人間が生まれた時からしている呼吸という営みを生かして演奏すること。
言われれば「なるほど」と思うことなのに、なかなかそれがてきていないこと、多いですよね。
そんなことをひとつひとつ教えてくれる一冊です。

▼全部まとめてメールで受け取る▼
※ezweb・docomo・vodafone・softbank.ne.jp・icloud.com・hotmailからのご登録の場合、文字化けやメールの配信エラーが大変多くなっております。恐れ入りますが、それ以外のアドレスからのご登録をお願いいたします。
(ご記載いただいた個人情報は適切に管理し、メール配信のための情報として利用させていただきます。ご本人の同意なしにその他の目的での利用・提供はいたしません。 )


